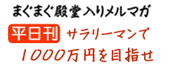投稿者 vastos2000 日時 2022年6月30日
「歴史とはなにか?」と聞かれたら、本書を読む前は「過去に起きた事を記録したものだよ」とでも回答していただろう。
私の場合、歴史をどうやって学んだかと言えば、主には学校で受けた教育からということになる。中学生や高校生のころは、教科書に書かれていることが誤っているなどという発想は持っていなかったので、主には受験のために太字で書かれている部分を中心に暗記したものだった。
歴史から思考の材料となるようなものを学ぼうという考えを持ったのは大学に入ってからで、年号を暗記することは時間軸をつかむという点で無駄ではないけれど、それよりは「何が原因で何が起きたか」を知ることのほうが重要だと考えていた。
その因果関係から、人の行動パターンや思考パターンを学ぶことができ、それを思考のための材料にできると思っていたからだ。
本書を読み終えても、歴史を学ぶ理由は上述のもので良いという考えは変わらなかったが、歴史に対する認識が変わった。
本書は前書きもなく、第一部が『歴史のある文明、歴史のない文明』であり、いきなり「歴史とはなにか?」という問いが投げかけられる。そしてそれを受けて『なにが歴史かということは、なにを歴史として認識するかということなのだ』とある。
ここでいきなり衝撃を受けた。「えっ、認識によるという事は、人によって歴史は違うの」と。
だが落ち着いて考えてみればそんなことは結構あるなと思い至った。NHKの大河ドラマにしても、従来は悪人のように思われていた人物が、実はいい奴だったんじゃないかというような描かれ方をしている作品もあるし、信長や家康も作品によって受ける印象が異なる。
現在の出来事でさえも切り取り方や編集によってずいぶん受ける印象は変わるから、今生きている人間は誰も見たことがない過去の出来事を、正確に、子細漏らさず記録するのは無理があると納得。
本書では史記や日本書記などが取り上げられているが、これも著者(編者)の見方や都合で書かれているので、プロパガンダのような一面がある。中国の歴史書は書かれた目的がその時代の王朝の正統を訴えるものであったから、その時代の文字を読める人々に対するプロパガンダだったのだろう。
4月の課題図書『戦争広告代理店』で学んだことだが、現代の出来事であっても、編集の仕方で視聴者や世論に与える影響は変わる。それは歴史書でも同じことが言えるだろう。なぜなら、その時代(過去)に行って、直接その出来事を確認することができないからだ。
司馬遷がどれだけ意図的にウソをついたり辻褄あわせをしていたか、私は知らないが、目的に沿って書いていたのだろう。(現実的に一人の人間が見聞きした出来事すべを記録するのは不可能)
史記も含めて、史料は意図的かどうかにかかわらず、ウソが紛れ込んでいるものだから注意が必要だと学んだ。
それを踏まえると、歴史から学びを得る際の姿勢が変わる。多少、ウソや誇張・省略があったからと言っても、どの出版社にも書かれているような史実は実際にあったことがほとんどだろう。そこから今も昔も人間の行動原理は大して変わらないことが学べると思う。
近年は欧米では戦争が起きていなかったが、ついこの間、ロシアがウクライナへ軍事侵攻した。出典は忘れたが、紀元後、地球上で都市や国家単位での戦争や紛争がなかった時期は、圧倒的に戦争が行われていた時期に比べて少ないということを読んだ。確かに日本国内だけ見ても、江戸時代を除けばしょっちゅう戦争をしていたので、それは本当だろうなと思う。つまりは、戦争が起きることは歴史を学んでいれば珍しいことでは無いとわかる。
ただ、心がけたいのは、教科書でさえも内容が訂正されるくらいなので、「ある史実や人物について学ぶなら、複数の資料を読むべき」という事だ。有名なものでは、鎌倉幕府の成立が、以前は1192年とされていたが、今は1185年とされている。
ある史料がプロパガンダを目的に書かれたものであっても、それを踏まえた誰かが研究した成果物であれば、それを読む我々も歴史を学ぶ意義も効果もあると思う。
特に、歴史を学ぶ目的が考える材料を増やすためであれば問題ない。『わが闘争』を読んでも、「ヒトラーはこういう考え方をしていたのね」と学びを得ることができる。
一方の立場から書かれただけを読んで「これが絶対の真実だ」と思うのは危険だが、それがプロパガンダである可能性を頭に入れて読めば「これを書いた人はこういう見方・考え方をしたのね」と解釈すれば良いし、同じ史実について異なる立場から書かれたものを読めばより良いだろう。
本書を読んだ事で、歴史書も人の手により書かれたものである以上は多かれ少なかれバイアスがかかっていることをハッキリと認識できた。
言われてみれば当たり前のことだが、言語化できていなかった。日中韓で歴史認識にズレがあることは承知していたし、国内に限っても右と左では太平洋戦争に対する考えが異なることを知っていたのに、上述したような事に思い至らなかった。本書から新たな見方を得ることができたので、今後は歴史に関するものを読む際は今までよりも良い吸収ができるだろう。感謝。