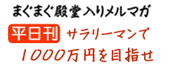投稿者 kawa5emon 日時 2019年11月30日
書評 サードドア アレックス・バナヤン 著
「可能性の技術」
これは、私が現在の会社に新卒入社し、営業キャリアの始まりとなる最初の営業所で、
当時の営業所長に営業の本文とは?と問うた際に、得た答えである。
本書を通読後、自身のこれまでを振り返り、この言葉を思い出した。今でも重宝している。
解説すると、会社の従業員の中で一番最初に市場及び顧客に接する営業は、
市場及び顧客にて何が起こっていて、今後はどうなるのか?その見極めはもちろんのこと、
売上計画を脇に抱えながらもその達成だけでなく、自社が発展、継続するためには、
それらの事象に対して、情報を一番最初に得る営業は何をすべきなのか?を表現している。
どこが種を植えるべき畑で、どのような種を植えればいいのか?また種を植えた後、
どのようにその種を育て見守り、芽を出させ、成長させ、収穫までもっていくのか?
その一連プロセスを考え実行するのが営業の本文という訳である。
先の言葉に私なりの補足を加えると、
「(市場にて自社成長の)可能性(を見つけ)の
(種を仕込み、育て、収穫にもっていく確度を上げる)技術(が重要)」
となる。この補足説明の、
「市場」を「自己のおかれた環境」、「自社」を「自己」に変えてみたらどうだろう?
この視点で本書を読むと、著者が経たプロセスの意味を理解できるのではないだろうか?
つまり本書には、与えられた環境からあらゆる自己成長の可能性を探り、
成長のための種を植え育て、芽を見つけ成長させ、どう収穫するのか?の過程がある。
本書で表現されているモノの価値として、あと二つ強調したいことがある。
一つは、成長までには必ず踊り場の時期があり、その時期は一見成果が見えないこと。
もう一つは、成果の本質が見えるのは、その取組みのかなり後ということである。
本書は、成果が見えない踊り場の描写が多い。それを失敗談で片づけると自己成長出来ない。
本書後半でクインシー・ジョーンズが語ったように「成功と失敗は同じ」も重要だが、
そもそも、他人の踊り場七転八倒物語は普段なかなか接することが出来ないにも関わらず、
挑戦する人は必ず直面する場面であり、著者の描写を通じ、自身も七転八倒を追憶出来た。
踊り場時期をどう理解し、我慢し、脱するのか?幾つかの実例が本書にはある。
次に成果の本質について。本書の一例で言えば、ビル・ゲイツとのインタビュー。
今の自分からすると、ゲイツの回答内容は鳥肌モノ以上の生告白と感じたが、
当時の著者には、それが何を意味するのか?理解出来ていなかった。
しかしその理解不足も、後々の学び、経験で理解できることになる。
ここで言いたいのは、理解が先か?経験が先か?ということである。
結論から言えば、理解よりも経験を優先すべきである。理由付け、理屈付けは後でいい。
理解を先にすると行動に移れない。ほとんどの場合、理解して行動に移ろうすると、
その場面自体が既に無くなっている。後悔したところで、その機会は二度と現れない。
一生に一度しかこの機会は無いかも?と考えれば、飛び込むしかないではないか。
飛び込んで未知の世界であればある程、その意味、理由を探すために脳が動く。
これが自己成長のための逆説的種蒔き。理解して飛び込んでも得られるモノは少ない。
更に言えば、一生に一度の機会を作り、飛び込まなければならない。著者はそうした。
その例示があり、疑似体験まで出来る点でも本書は秀逸で、そのフレームは応用が効く。
さて最終的に、サードドアとは何なのか?
それは貴方のための、貴方だけのドアである。冒頭にあるようにいつでもそこにある。
セカンドドアは生まれた時点で与えられている。本書はここをターゲットにしていない。
自身もそうだが、ここで一番気にすべきは、ファーストドアだろう。
これが理解できなければ、本書定義のサードドアも理解できない。
ファーストドアを換言すると、他人との比較軸で発生しているドアである。
発生させたのは貴方だ。なぜなら、そのドアを選択したのは貴方だからだ。
理解の上でファーストドアに向かってもいいが、果たしてそれで貴方は幸せだろうか?
私の答えはノーである。自分のためだけのサードドアを常に探している。
しかし本書を通じて、意識はサードドアに向かいながらも、日々はファーストドアへ
多くの取組みがつながっていることが確認できた。それは著者の赤裸々な記述のお陰だ。
本書が定義する、誰も教えてくれないサードドア。自ら目標を設定、そして考え行動し、
その結果全てを自分事として捉えられるか否か?やっと最近それがわかってきた。
そして本書を通じ、そのドアまでの過程を仮想体験出来た。
もし今後行き詰まる場面に出くわしたら、再度本書で自分を客観視します。
今回も良書のご紹介及び出会いに感謝致します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。