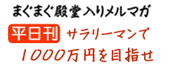投稿者 H.J 日時 2022年4月30日
本書は、1990年代のボスニア・ヘルツェゴビナ紛争における広報戦略の裏側を描いたドキュメンタリーである。
ジャーナリストである著者が取材を基に書き上げた本書はドキュメンタリーでありながら、構成の巧さが引き立ち小説の様にスラスラと読めた。
PR活動の極意や分析の仕方も解説されているため、見方によってはビジネス書の様にも読める。
ただ、私は怪しい系にも通ずる部分がある様にも感じた。(この部分は後半で述べる)
凄く奥の深い本だと思った。
全体を通して、まず私が驚いたのは、国を挙げての広報戦略を民間企業がリードしてPR活動を推進していく事だ。
もちろん、ボスニア国も最初から民間企業へ依頼しているわけではなかった。
当初は「この紛争を"国際化"し国際社会を味方に付ける」という目的を掲げ、地道に首脳への説得を試みた。
しかし、状況的に切迫詰まり、結果も乏しかった状態で独立直後の小国だったボスニア国にとっては選択肢が限られた状態だったとも言える。
ボスニア国が協力を要請したのは、フィリップス氏から紹介されたアメリカのPR企業ルーダー・フィン社の幹部社員ジム・ハーフ氏。
彼はメディア関係者や政治家への対応も熟知しており、自身の信条を基に適切かつ誠実なコミュニケーションで各方面からの信頼を獲得した。
具体的な方法としては、最新情報を出し続け、掲載内容を拡散し、味方となるメディアを絞り、記者やジャーナリストに対してお礼など、小さな努力を積み重ねた。
そして、政治家も信頼を寄せて提案されたPR戦略を全うし、ハーフ氏が伝えたいことがスムーズに伝わる。
土台が出来上がると次はターゲットとするべき相手の心を揺さぶる「民族浄化」というパワーワードを巧みに使用し、大衆の感情を動かした。
その結果、世論はボスニア側に付き、ボスニア国の思惑通りボスニア紛争は只の内戦ではなく、世界の国々を巻き込んだ。
ここまで見ると「全てが嚙み合って大成功だった!凄い!」となるわけだが、これで終わったらただの要約になるため、ここから持論を述べる。
本書のテクニックは広報活動には勿論のこと、怪しい系にも通ずる部分もある様に感じた。
なぜなら、P11で著者が記述している様にこの紛争では、PR活動による情報戦、所謂"虚"の戦いが実際の人々の血が流される"実"の戦いに大きな影響を与えている。
言い換えると、情報という目に見えないもので現実世界を動かしたのだ。
ここで情報に対して目に見えないと定義したのは、実際に戦場にいない人達が目で見ていない情報という意味からだ。
また、情報というものは目に見えないが故にグレーゾーンである。
フェイクニュース等が存在する様に、その情報が必ず正しいとは限らない。
結局は受け手が自分の頭で考え、その情報を正しく理解する必要がある。
このあたりも怪しい系に通じる様に感じる。
話を戻すと、ハーフ氏は正しい方法で地道なPR活動の末、一つのことがきっかけ(今回の場合は民族浄化というパワーワードで世論が動いた)で現実世界を思った方向に動かした。
これはもちろん、ハーフ氏のPR活動における理論や冷静な状況判断力もさることながら、シライジッチ氏が行動したことにおける結果だ。
理論と行動が両立したからこその結果である。
もしも、このどちらかが欠けていれば戦況は変わっただろう。
そして、ハーフ氏はボスニア人にとっては英雄と言っても過言ではない存在になった。
しかし、見方を変えれば、ハーフ氏のPR活動はセルビア側にとって悪なのである。
戦争の流れを変えた"民族浄化"というワードはセルビア人の虐殺を非難するためのプロパガンダだ。
このワードさえなければ、きっと死ななかった人達もいただろう。
この一言で良くも悪くも運命が変わった人は沢山いるだろう。
ただ、これについては、運的要素もあるので、仕方ないところではある。
逆にこの一言で存命した人も沢山いるだろうから。
勝てば官軍負ければ賊軍という言葉がある様に、戦争というものはこういうものだと受け入れるしかない。
勿論、ハーフ氏にとってみれば仕事を全うしただけなのだから第三者が責められる筋合いはない。
それよりも私が怪しい系に通ずる部分があると濁したのは、この部分があるからだ。
使い方(視点)を誤ると悪の道そのものである。
だからこそ、必要なエッセンスを抽象化して、利用するかしないかを自分の頭で考えて実行する必要がある。
そんなことを感じた一冊だった。