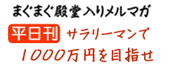投稿者 mkse22 日時 2022年5月31日
「同志少女よ、敵を撃て」を読んで
本書では主人公であるセラフィマの視点から独ソ戦の様子が描かれています。
彼女は故郷の村をドイツ兵に襲撃されたことをきっかけにドイツ兵とイリーナに
怒りと殺意を覚えつつ、ソ連軍の狙撃手として独ソ戦に参加、数々の戦果をあげていきます。
彼女は兵士としての経験を積む中で、戦う理由が変わっていきます。
当初は自分の村をおそったドイツ兵を殺すためでしたが、次第に味方や女性を守るためとなり、
最後には、味方より女性を守ることを優先します。
彼女が女性を守ることを優先するきっかけとなったのは、味方の男性兵士がドイツ人女性を
襲っている場面に遭遇したときです。その場面に遭遇した彼女は、敵国女性を守ることを優先し、
女性を襲っていた男性兵士を射殺します。味方兵士を射殺したことが判明すれば、
自身が処刑される可能性があるにもかかわらずです。
この事例には男性兵士と女性兵士の違いが凝縮されています。
男性兵士と女性兵士の違い、それは仲間意識と倫理観にあります。
男性兵士は、特に同性兵士との仲間意識を重視しており、仲間意識向上のために
女性への暴行といった違法行為を手段として利用するほどです。
女性兵士にも仲間意識はあるのですが、敵国の女性や子供を助けるために必要であれば
仲間を裏切ります。
仲間意識と倫理観の違いが彼らを対立させます。
女性を襲うことはどんな理由があっても許されないことだと主張するセラフィマに対して、
もちろん許されないことではあると理解しているが、仲間意識向上のためにやむをえないことであり、
さらには特殊な環境が普遍的な倫理を捻じ曲げて無効化してしまうと主張するミハイル。
改めて女性への暴行は絶対に許されないと主張するセラフィマに対して、彼女が80人もの敵兵を殺していることを指摘して、
普遍的な倫理は存在しないことを指摘するミハイル。
ミハイルの指摘に対して、嫌悪感をあらわにして会話を打ち切ったセラフィマ。
ここに男性兵士と女性兵士との間に理解しあえない壁があるように感じました。
この対立は男性と女性という性別が起因しているのでしょうか。
たしかにそうかもしれません。ただ、男性と女性という視点が大雑把すぎる可能性があるため、、
さらに詳細な視点からの分析、例えば、大人や子供や障害者やLGBTであればどのような考え方をするのか
調査する必要があるとかんがえます。
ただ、この対立の背景として独ソ戦は男性の戦争であることを考慮する必要があるかとおもいます。
独ソ戦は、将校や兵士の大部分が男性のため、男性の考え方や価値観が
軍の作戦や行動に強く反映されてしまっているからです。
このことは次の1文に集約されています。「戦争は女の顔をしていない」(p.471)
仮に、女性の戦争が発生したら、女性はどのような状況となるのでしょうか。
例えば、軍の将校や兵士の大部分が女性で構成されている国同士が戦争をしたらどうなるのでしょうか。
もしかしたら、女性にとっては、男性の戦争を超えるような人権侵害を受けるような状況になるかもしれません。
なぜなら、女性を最も理解することができるのは同じ女性です。
軍の女性将校が作戦を立てる際に、勝利のために女性固有の考え方や行動を十分に考慮するはずです。
同じ女性だからこそ女性特有の弱い部分がどこかがわかるわけです。
それでは女性の戦争では、女性の暴行はどのような扱いとなるのでしょうか。
セラフィマの主張の通り、どんな理由があっても許されないことだとして
両国の間で合意がなされて禁止事項となるのでしょうか。
正直、どちらも起こりうる可能性があるかと思います。
女性同士だからこそ、絶対に許されないことだとして合意することができるかもしれませんし、
もし、戦況が悪くなれば、女性将校はたとえ禁止事項にしていたとしても敵国の女性兵士を追い詰めるために
解禁するかもしれません。
女性の戦争では実際に実際に戦うのは女性のため、敵国の女性を追い詰めることができれば、
その軍の戦力を直接的にそぎ落とすことができます。男性の戦争における女性は基本的に戦わないため、敵国女性を追い詰めても、
軍の戦力にそれほどの影響はありません。こうなると、女性同士の対立構造が生まれてくる可能性があります。
このように考えると、先程の仲間意識と倫理観の違いというのは、男性の戦争という特殊な前提のもとで成り立つものであり、
実はそれほど強固な違い可能性があることに気づきました。
本書を通じて、改めて、視点を変えることの重要性に気づきました。
今月も興味深い本を紹介していただき、ありがとうございました。