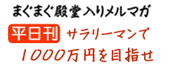投稿者 mkse22 日時 2021年8月31日
満州とアッツの将軍 樋口季一郎 指揮官の決断を読んで
本書を読んで、最も印象に残ったのはオトポール事件だ。
オトポール事件とは、ナチス・ドイツのユダヤ人狩りから逃れ、
ソ連領のオトポールに出現したユダヤ人難民に対して
当時ハルビン特務機関長だった樋口が独断で満州国への受け入れを
認めさせた事件だ。
当時、日本とドイツは日独防共協定を結んでおり、良好な関係であった。
その中で、樋口はヒトラーのユダヤ人追放に対して反抗したわけだ。
この判断をした理由として、彼はは回想録の原文の中で2つ
(①彼自身の人道的公憤と②対ユダヤ関係の緊密化)挙げている。
ただ、後でこれらに斜線を入れて取り消しているが。
この樋口の行動に、①と②が理由として正確ではないが嘘でもないという気持ちが
透けて見えるようだ。
すると次に樋口の本音はどちらに近いのかという疑問が湧いてくる。
本書では、そのどちらでもなく、知り合いのユダヤ人を助けたいという素朴な感情だと
推測している。
それでは、①と②は、本音に対してどういう位置づけのものになるのかと考えると、
周囲への説明向けとしての理由なのかもしれない。
周囲を説得するための理由というわけだ。いわば、建前である。
たしかに、難民受け入れを周囲に認めさせるためには、知り合いがいるから助けたいだけでは
不十分で、建前としての①のような人道的理由や、②の経済的理由が必要かもしれない。
そして、①と②は本音と乖離しているから、あとで斜線を入れたのかもしれない。
この樋口の難民受け入れ理由は、現代ドイツのそれと酷似している。
現代ドイツも難民受け入れに積極的であり、それを国民を説得する理由として
人道的理由とともに経済的理由を挙げている。
ドイツは戦後、ナチスへの反省から抑圧されたものを受け入れる方針を掲げ、
難民の受け入れに積極的となった。
ただ、当初から人道的理由だけでなく、経済的理由もあったようで、
自国の労働力不足の穴埋めのために難民を利用したいという計算も入っているようだ。
最近のドイツでは難民に対する教育を恩恵ではなく投資と見做しているとの記事を
読んだとき、なるほどとおもった。
ただ、難民の受け入れには、メリットだけでなくデメリットも存在する。
例えば、難民が受け入れ先に溶け込むことができずに両者が衝突する可能性があるからだ。。
その衝突の一例としてドイツでは2015年に発生したケルン大晦日集団暴行事件がある。
同事件をきっかけに難民受け入れの方針が一時期変わった。
2016年には保守系政治家が任民の受け入れに上限を設けるように主張したそうだ。
現在は、元に戻りつつあるようだが。
さらに難民受け入れのためには、教育など一定の費用が必要で、それはドイツ国民の負担となる。
現代のドイツでも政治家が人道的観点のみで難民受け入れを主張しても、国民全員の同意を得ることは難しいようだ。難民問題は常に選挙の争点となっているからだ。だからこそ、経済的利益など別の利益を主張するわけだ。
このように、難民受け入れ理由について樋口と現代ドイツは同じものを掲げたわけだ。
人権意識が高い現代国家と同じ理由を挙げた点に、樋口に先見の明があったように感じる。
もちろん、違いもあり、それは本音の部分だ。
樋口の本音は知り合いの人を助けたいという気持ちであり、
ドイツは、当初はナチスへの反省と言われているが、現在は不明だ。
本音が経済的理由になっているかもしれない。
樋口の回想録に次の言葉がある。
〈世の中には絶対の善もなく、絶対の悪もない。善悪は相関的なものである〉 (Kindle の位置No.2915-2916)善悪は相対的なものであり、善の反意語は悪ではなくもう一つの善である。
この言葉から、①と②に斜線を入れた別の理由を推測可能なのではないか。
例えば、樋口は①と②を善と考えていたが、後世から真逆の評価をされる可能性があることに気づき、
そのことは自身の本音からは大きく乖離するため、あえて斜線をいれたのではないかとかである。
ただ、仮に本音を書いたとしても、それ自体が、時代によりが真逆に評価される可能性もあるわけで。。。
言葉で伝えることが如何に困難であるかの良い例だ。
戦後、樋口が戦争中のことをあまり語らなかった理由はここにあるのかもしれない。
今月も興味深い本を紹介していただき、ありがとうございました。