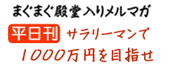第73回目(2017年5月)の課題本
5月課題図書
漂流
私は冒険ものとか、危険をかいくぐって生還するたぐいのノンフィクションが
好きなんですが、本書もまさにそんなノンフィクションでなんと37日間太平洋を漂流して
助かった人の話なんです。
これだけなら、似たような話がいくらでもあるんですけどここからがスゴい。なんとその
8年後にまたまた海に出て、今度は帰って来られなくなっちゃうんです。一度漂流するだ
けでもレアな体験なのに2回もやっちゃうとは・・・っていうか、よく2回目の航海に出よ
うと思ったよなぁというその心境を味わいながら読んで下さい。
【しょ~おんコメント】
5月優秀賞
先月の読書会で「再読したら一度目では見えなかったものが見えるようになるよ」と
言ったら、それがフェイスブックで回ったらしく常連さんたちが再読をしてから投稿して
くれました。再読しただろうなと思われる人の投稿はやっぱり読ませるものが多いですね。
いつものように一時審査を通過した人を書いておくと、tsubaki.yuki1229さん、
audreym0304さん、saab900sさん、そして番外としてjawakumaさんを選びました。番外と
いうのは感想文のコンテンツが優れているとか、なるほどと呻ったとかではなくて、読書
の楽しみがストレートに伝わってきたという意味で、面白かったなという意味です。
そしてこの方々の投稿を再読して今月はaudreym0304さんに差し上げることにします。お
めでとうございます。
【頂いたコメント】
投稿者 hiroto77 日時 2017年5月21日
【考察・本村実が再び漁に出た要因について】
この本のテーマであり、この著者が追求した「遭難から救出された本村実が、なぜ、再び漁に出たのか」について、抽出したキーワードをもとに、追想しました。
・キーワード1「漂流」
海での遭難にはいくつかの種類がありますが、航路を見失い、自立航行により帰港および陸地への到達が不可能な状態を意味するのが「漂流」であると理解しました。
このルポの対象となった本村実氏は、通常では生還が難しい極限状態から戻った経緯と、再び行方不明となっている現状の特異性から、題材として選ばれています。
今までの「漂流もの」と、この本との相違点は、「漂流による惨状と奇跡の帰還」に焦点があるのではなく、「壮絶な経験と記憶を乗り越えて、再び漁へ出た動機と、現在行方となっている事実」に焦点があることを、このキーワードから確認しました。
そのうえで、「漂流した極限状態の検証」を追究するのみでなく、そこにあった「再び漁を出た動機」を強く意識しながら、読み進めることとしました。
・キーワード2「海洋民・池間民族」
私は長野県の出身なので、海で働くこと、漁業を生業とすることについての知識、感覚が全くありません。
今回、「海洋民」ついての認識、とりわけ沖縄の風土と民族としての歴史が結びついた「池間民族」の情報について、この本により、新しい知識を仕入れることができました。
そこから、海洋民としての冒険者たる血筋、DNAに刷り込まれている海と結びつきが「再び漁に出た」動機と無関係でないことを、連想しました。
通常、現代社会に暮らす私たちにとっては、日本の狭い島国の中で、祖先や民族の違いによるギャップや価値観の相違を感じなくなっているのですが、「仕事」や「生業」において、「その違い」が如実に現れることは、経験と学びから確認しています。
そして「農耕を基本とした先祖をもつか」、「狩猟を基本とした先祖をもつか」を根拠としたセグメンテーションは、仕事に対する認識だけでなく、思想や自己理解の深いところでも分岐が現れる要素だと、認識しています。
本村実氏は、明確に海洋民としてのDNAを備え、漁業を生業とする社会に生きている点で、再び漂流するかも知れないという恐怖よりも、海とともに生き、海に魅せられた民族としての本性が勝ったのではないかと、推測しました。
・キーワード3「マグロの時代」
動機の素地として、受け継がれてきた海洋民としての要素があるなら、次に来るのが現代社会での欲求、経済的欲求を満たす、「短期で儲かる」という事実です。
「一度出れば、半年は働かない」「金融機関が不正を手伝っても貸し付けたい」などの事実は、その経済的意味合いと、沖縄の風土と民族性に適した仕事であったことを、教えてくれます。
「南国気質」という言葉は安直ですが、仕事を生きる動機と考えるのではなく、生きる手段として捉え、酒と享楽を選択する気質は、北東の山の民よりも南西の海の民のほうが強い傾向にあると、考えています。
自分の命と家族の生活を賭けた一発勝負で「儲けた」記憶と感情は、その後の行動に強い影響力を持つと推測されます。
そこには「ギャンブル依存症」に近い感覚が、「遠洋漁業」には存在すると感じました。
これが、再び漁に出た動機として、存在したと考えます。
・キーワード4「サードマン」
最初の「漂流」で救助されたフィリピン人船員の証言のなかで、とりわけ興味を惹かれた言葉です。
遭難者が飢えと絶望の極限状態で見出す「第三の存在」を表していますが、この存在を確認したのは、このフィリピン人だけだったのかという疑問です。
脳の生存機能による作用であるという研究もありますが、今回、その現象は、本村実氏には現れなかったのか、現れていたとしたら、どういうやりとりであったか。
取材や証言からは、それは確認できませんが、本人が語らなかっただけかもしれない、という妄想は「隠された動機」を探る上では、面白いと感じました。
・キーワード5「最初に食べるのは船長」
同じく救助されたフィリビン人船員が明言し、本村氏自身も証言している「人喰い」ですが、この行為と、民俗学における「カンニバル」という習性が結びつきました。
王となり超越者となるための行為としての「人喰い」、飢えをしのぎ、生き延びるための「人喰い」については、動機や背景は全く異なりますが、行為そのものと「王を喰らう」「支配者を喰う」という点で、共通点があります。
海上において、船員の命に対し責任を負う「王」である船長を「喰う」という行為には、人間の太古の記憶が隠されており、その発露がこの行為だったと考えると、再び漁に出たのは、王として、再び君臨することを、本能に近い部分が望んだ結果だったのかもしれません。
この一連の追想により、極限体験をしてもなお、海に出た人間の動機を窺い知り、人間の不可思議さの要因を、学び知り、想うことができました。
【了】
投稿者 tsubaki.yuki1229 日時 2017年5月26日
『漂流』
これは、読まなければいけない物語だ。
そう感じたのは、本書が「人間」と「自然」の関係を読者に考えさせ、圧倒的な力で、我々の意識を自然に対峙させるからである。
自然の力は偉大である。地震にしろ台風にしろ、災害が起こる度、その巨大な力を前にして我々人間は為すすべもなく立ち尽くしてきた。もちろん科学技術の進歩により、ある程度は自然を人為的に操作できるようになったのも確かである。だが21世紀になってからも、本村実船長は漂流し、いまだ行方不明のままである。いかに文明が発達しようと、この先、自然の偉大さが変わることはないであろう。都会暮らしをしていると、自然の恐ろしさを忘れてしまう自分は、もう一度、自然に対し畏敬の念を掘り起こさないと危険だ。・・・本能的にそんな危機感を覚えた。
本村実が漂流から奇跡の生還を果たして8年後、再び漁に出たのはなぜか?
・・・本書で繰り返される問に、私が漠然と出した答えは「本村、もとい漁師達と、海の結びつきの強固さ」である。漁師達と大海原の切っても切れない関係は、まさに人間と自然の関係の縮図である。
本来、人間は自然を、好き嫌いや善悪で評価することはできない。我々は、自然の恩恵を享受し自然に生かされることもあれば、逆に自然に命を奪われることもある。海で生死の境を彷徨った本村実が、その経験が原因で海が嫌いになったか?と言えば、答えはノーだ。本村実が再び漁に戻ったのは、文字通り「海で生きる以外、生き方を知らなかった」からなのだろう。
与えられても奪われても文句を言えず、縁を切りたくても切れない。この関係は、血を分けた親子の縁にも似ている。海で苦労をして文句を言っても、海に惹かれ、海に戻らざるを得ない・・・という感覚は、理性でなく帰巣本能に近いとも言える。
だからこそ、彼ら漁師達は海に対して、私達「陸の人間」が信じられないほどに、恐怖や憎しみの感情を持たないのではないだろうか。
アメリカ古典文学に『白鯨』という小説がある。これは、巨大クジラに片足を食いちぎられた過去を持つ船長が、その巨大クジラに復讐を誓い、憎しみを募らせ、数年にわたって船員たちを巻き込みその巨大クジラを捜索する、という話である。船長は結局、クジラと死闘を繰り広げた結果、破滅する。
この船長と『漂流』に登場する漁師達は、何と対照的なことか。漁師達は、ダイナマイト漁のような危険な作業で大怪我を負おうとも、家族や仲間を海で失おうとも、「自然(海)がやったことだから、恨んでも仕方がない」と、ある意味達観した姿勢を貫いている。一方『白鯨』の船長は、クジラを悪魔呼ばわりし、復讐の鬼と化した狂人である。はっきり言って滑稽でさえある。このマインドセットでは、一生幸せになれないだろう。彼を見ていると、憎しみにとらわれて生きるのは時間の無駄だと感じてしまう。これが『漂流』の漁師達ならば、クジラに足を食いちぎられても
「クジラも腹が減っていたんだよ。お互い動物同士なんだから、生きるために仕方なくやったことだろう。恨んだって仕方がないさ」
と考えるのではないだろうか。文学とノンフィクションを比較するのは強引だが、このコントラストは、自然を征服しようとする西洋人と、自然との共生に努めてきた日本人の、精神性の違いを表しているようにも思える。
最後に、『漂流』の最終章で、カニバリズムが言及されたことが印象的である。
筆者は、例えどんな極限状態にいようと「人が自らの生存のため、他の人の肉を食べる」など、信じたくなかった。そのため、一度目の漂流の時、フィリピン人の8人の船員達が一瞬でも「本村船長を殺して食べよう」と思った、という事実が発覚した時、それが俄に信じられず、葛藤する。
私自身には、筆者の角幡氏のような葛藤はなかった。「それは大いにあり得る」と思ったのだ。サンデル氏の『白熱教室』(しょうおん先生の良書リストの一冊)第二章にも、他の船員に食べられたリチャード・パーカーの実話がある。
私達は、陸の文明人の常識に囚われ、海の漁師達の生き方や哲学について、自分達の価値観でくくって考えてしまう傾向にあると感じる。例えば私は「海亀を逃がしてあげたから助かった」と本村氏のインタビュー記事も、まるごと嘘とは思わないが、新聞記者がストーリーを読者ウケするように脚色したのではないかと疑ってしまう。
私達は日頃から、あらゆる空想に、耐えておくべきだと思う。特に、自分と全く異質で過酷な世界こそ、常識を捨てて、素直な目で見つめるべきなのだろう。なぜなら、人生は想像を超える出来事の繰り返しだからだ。自らが身をもって経験できることは限られている。ならば、本を読んで自分の世界を広げることが、絶対不可欠である。
最後に、一言で「沖縄県」といっても、沖縄県は多くの小さな島で成り立ち、一つ一つの島に少数民族が住み、異なった言語(方言)や豊かな文化を持っていることを知ったことも、非常に大きな収穫だった。素晴らしい図書をお薦めいただき、ありがとうございました。

投稿者 audreym0304 日時 2017年5月26日
感想-漂流
本書を読んでいるとき、イメージしたのは圧倒的な海の存在だ。それも砂浜や入り江ではなく、360度海しかない湾曲した水平線しかみえない海だ。
本村実氏が何を感じたのかを考えた。背筋が凍りつくような深い恐怖、その恐怖をもしのぐのは全てを超越した神の御許である海に抱かれて全てを運を天と海に任せ安心感にも近い気持ちだった。池澤夏樹氏の児童小説『南の島のティオ』にでてくる数百㎞離れた故郷に帰るため一人で手作りのカヌーに乗り海を渡った少年の後ろ姿がよみがえってきた。
小説の中で一人海を渡った少年もしかり、本村氏をはじめ、自らを池間民族と呼び、先祖代々海とともに生きて死んできた人にとったら、常にそばにある海は生きる糧を与えてくれ、嵐や津波で与えてくれた恵みだけでなく命も生活そのものも奪い去ってしまう。人間の意志なんぞはるかに及ばない存在で、生きることも死ぬことも海があるからこそであり、男も女も大人もこどもも海があることで自分たちがあるのだろう。
作家池澤夏樹氏が新聞のコラムで沖縄は東南アジアの最北端という記載をしたことがあった。地理的・気候的・文化的に見たときの特性を言い表したのだが、海洋民族が育んだあっけらかんとした感覚、思想、ある意味宗教的ともいえる死生観のつながりでも沖縄は東南アジアの最北端といえるし、池間民族には顕著のように思える。
那智勝浦の海岸から出発した補陀落僧が生きてたどり着ける最南端が沖縄だったと考えると、海洋民族的感覚と西方浄土の思想からニライカナイという海の果ての楽園は生み出されたのは、いくら海洋民族でも海のほとんどが未知だったからだ。その海の向こうに浄土があるなら海で死ぬことは畏れることではないと思っただろう。考えてみれば、先史時代にすでに人類は大海原に漕ぎ出している。漕ぎ出した先にたどり着ける先があるかもたどり着けるかもわからないのに。それは補陀落僧にも冒険者にも似ている。
本村氏がフィリピン人船員と違ってどこか達観したような雰囲気があったり、家族や親せきが「どこかで生きている」とおもうのにもニライカナイ思想と先史時代から受け継いだ遺伝子がが一役買ったに違いない。
東南アジアやアフリカではいまでもダイナマイト漁は違法、危険と知りながらも続けている人たちがいる。昔ながらの生活を続けることができるのであれば、家族や地域で必要な分さえ取れればよかったのだろうけど、生活のすべてが経済社会に組み込まれている現代では魚を売って少しでも現金にするための生活手段なのだろう。それだって危険を伴う実入りの少ない割の合わない労働だ。
海洋民たるもの海の仕事に従事し、長期の漁に出ることも、長く家を空けることも、漁の最中に漂流し、命を落とすこともある意味仕方がないと思うかもしれない。今や遠洋に出ていく多くの海洋民が海に出稼ぎに行かなければ行けない事情が経済的な理由だし、それもオイルショックやさまざまな国際社会の事情と切り離せずにいることはきっと海洋民にとって大きなフラストレーションでありストレスだろう。
小説で多く書かれるように遭難者や漂流者が生き延びるために死んだ人間の肉を食べることや誰かを犠牲にしたことは昔からあるのだろう。本村氏も実際にフィリピン人船員から「あんたから真っ先に食う」といわれ、噛み付かれてはいるが、もし仮に、フィリピン人船員に襲われて食べられたとしても、海で生きる人間の本懐とおもえるのだろうか。食べられたとしても海洋民としての魂は海や食べた人に引き継がれるような気がしてならない。それは従来の意味の「死」とは違うように思う。
ウミガメを捕まえたものの食べずにひっくり返ってばたばたしているのを見て海に返したというエピソードも印象的だ。明日の生死もわからない人間がここでカメを食べても救助の確証もないのに生き延びることへの恐れがあったかもしれない。バタバタと必死で生きようとしているウミガメに強い生命力を感じて、死に近づいている人間には歯が立たないと思ったのか、このあと救助にあえず海で死ぬことになったらウミガメに申し訳がたたないとおもったのか。とにかくウミガメの生命力に歯が立たなかったのだろう。
本村氏をはじめ多くの漂流経験者がなぜまた海に戻るだろう。漂流だけではない、火事やその他の事件・事故が海の上の船という密室で発生すると船長のミスなのだし、そのミスをしてしまったのだから、海洋民としてのプライドは深く傷ついたにちがいない。海洋民だからこそ、海への畏敬の念は持ち合わせているだろうが、海に出ることは当然なのだ。だからこそ、海洋民である彼らは海がそばになければ生きていくことも生きている実感も持てない。陸では生きていけないのだ。あえて言えば、彼らが海に戻る理由は「そこに海があり、海でなければ生きていけない」からだ。
投稿者 Nat 日時 2017年5月28日
何の予備知識のないまま題名を見ただけでワクワクするような本はめずらしく、一気に読んでしまいました。なぜなら昔から漠然とした海に対する憧れというものがあるからです。
そんな憧れから幼少のころは15少年漂流記や宝島等のいわゆる海洋冒険物小説を何度も何度も読んでいました。
しかしそんな小説とは違う「リアルな漂流」「リアルな海」が描かれた本書を読んだ後は、海に対する憧れとは別の知識がインストールされました。それは海を生活基盤にする人たちの生き様であったり、海という自然環境の厳しさであったり神秘さであったりというものです。
特にダイナマイト漁を行っていた漁師たちの生き様はとても強烈で、陸を生活基盤とする我々とは大きく異なった死生観を持ち生きていたことを、まざまざと見せつけられました。
そんな海洋民族特有の生き様を追っていくと本書を読み始めの頃には理解できなかった本村実氏がもう一度海に出た理由もなんとなくですが、わかるような気がするんです。陸での生活では自分が生きている感覚がなかったのではないか。ある意味生きた屍のような鬱々とした気分の中で生きていたのではないか。そしてもう一度自分の生を実感できる海に飛び出した。そんな自分の世界に帰り、陸に戻ることは二度となかった。
人によって生き様は違う。頭ではわかっていても普段我々はどうしても自分の頭の中の価値観、尺度というフィルターを通して他人を見てしまいます。しかし陸で生きる我々ですらも、生き方が違うことにより、その価値観、尺度が微妙に違うんですよね。
この本で書かれている本村実氏や他の海に生きる人達のような、陸での生活とは180度違う生き方をしている人々の生活に触れることで、その他者との感覚の違いを時々でも良いので再認識、調整してあげることが必要だと感じました。
投稿者 lazurite8lazward 日時 2017年5月28日
価値観を逆転するきっかけを与えてくれる素晴らしい書籍。
海は好きだけれどもサメが最大の天敵と思っている私にとって、37日間の漂流はどれだけの恐怖があるのか想像しきれません。しかし、この書籍で一番インパクトがあったのは著者がマグロ漁船に乗って取材しているという点。少々釣りが好きな人などでも流石にマグロ漁船に乗るのは躊躇すると思うので、この著者の方はどのような人?と思ったら探検家の方なんですね。どうりで取材の旅程がタフなわけです。
著者の方は、かなり様々な探検をされているようなのですが、それにしてはこの「漂流」の視点が探検家らしくないなというのが正直な感想。気付きを与えてくれたのは主に次の2点。
1つ目は、『大漁船と不漁船の違いがどこにあるか私には謎だった』と著者がコメントしている点。よほど強運な星の下に生まれない限り理由のわからない運・不運は日常茶飯事だと思うんですよね。特に海にまつわるものについての運・不運はかなり一般化しているように思います。分かり易い事例だと釣り。海釣りでも丘釣りでもあちらこちらでほとんどの人が釣れているのに自分だけなぜか当たりが無い、なんて事はしょっちゅうあることで、やっと当たりがきた!と思ったら他の釣り人の糸が釣れてた・・・。修復作業してたら魚群はとっくにはるか彼方でそのまま撤収というのはよくある話。大間のマグロ漁師が3年間全く釣れないというのがテレビ番組の企画のセンターになるくらいです。造船という領域でも命名から進水式の儀式まで念には念を入れて縁起を担ぎまくるというのは常識。進水式で何か粗相があればそれはもう大変、狭い世界ですから船員は出港前から気もそぞろになりかねません。ヨットで太平洋を横断するくらいの経験を持つ著者であったら、船長と船の相性は1番気にしたのではないかと推測。同じ材料で同じヤードで同じ型式の船を造っても、それぞれ全く別物であるのは周知の事実ですので、著者の方は相当な強運故にあまり不運に見舞われることがなかったのではないかと想像しました。私は時々空を飛びますが、海の人達と同じように縁起やルーティーンを大切にしています。空の場合は、海の様に遭難ということは少なくエマージェンシーの際には即命に直結します。故に、その日身に着けるものや食べるものや事前準備などは、変えないようにしています。そうすることで、何か少し違う違和感を察した時にそれを正確に把握し危機的な状況を事前に回避したいからです。船の遭難でも、そのような予兆というのはきっとあるのだと思います。今回の書籍で言えば遭難中にウミガメを海に返した部分。実際ウミガメを海に返すことが何に影響したかわかりませんが、そのような行為が、その後の現実にどのように影響しているか察し直感に従うことは非常に重要なことだと改めて思います。
2つ目は、著者が海洋民と命名している点。『マグロ延縄漁船の船長を長年やっていると仕事ではなく、生き方や人格になってしまう』、そしてそれが故に海洋民は陸に戻れないという考え方は少し解釈が違うように思います。(人によって幸せは違うとは思いますが)仕事が生き方や人格に直結するというのはかなり理想的な事で、人生の多くの時間を費やす仕事が生き方や人格と大きく離れてしまっているというのはあまり理想的なことではないはずです。著者は、海洋民は陸にもどれないとしていますが、解釈は正反対だと考えます。本来陸の人間も海洋民のように「仕事を生き方や人格と直結させたい」けれども責任を他者に委ねて管理された枠組みの下で生きる陸の世界に(多くの人が)染まってしまっているので、仕事を生き方や人格と直結させて自己責任の下での自由を手にすることを忘れてしまっている。一方で、海洋民は自己責任故の自由と、仕事が生き方や人格と直結する理想的な生き方が目の前にある。従って、管理された陸の枠組みの下へ戻るのはまっぴら御免というのが本質なのではないでしょうか。主人公は漂流後にまた船出する訳ですが、海だから遭難・漂流するという訳ではないように思います。陸では物理的に漂流するということがないのでわかりにくいのは確かですが、人生という大きな流れでみたときには致命的な漂流(失職や大ケガや山で遭難など)に陥ってしまうことが少なからずあります。海でも陸でも致命的な漂流に陥らないようにするには、自分を磨いて感性を高めるしかない訳で、主人公をはじめ海の人たちはそのフィールドが目の前に広がっているため、人生への立ち向かい方が感覚的に分かっているのだと思います。故に主人公は、結局海にいようが陸にいようが、ダメ時はダメだし良い時は良いので自分の感覚に従って遭難後もまた海に出るという判断をしたように感じます。
陸にいても海で遭難するが如く窮地になることはある訳だから、日々の生活も大海原にいるつもりで生きていないとダメだよと諭されるような内容でした。
投稿者 satoyuji 日時 2017年5月28日
『漂流』感想
どうしてこんなにも苦しい生活を続けたのだろうか。それが本書の漁師たちへの第一印象だった。海で生きるということは常に死と隣り合わせなのに、それでも海の仕事以外を選ぼうとしない。「他にできることがないから」という言葉が何度ともなく挙げられるのを読んでいて、2015年12月25日に自殺したと報道されていた電通社員の自殺報道を思い出した。私はこの事件について詳しくはないが、もっと楽な選択肢があるはずなのに選ばなかった点で同じように思えた。他の選択肢はなかったのか、絶対にあったのではないかと思えてならなかった。
虐待された子どもは、自分の子供に虐待を繰り返すという。それと同じなのかもしれない。自分がそれをやりたくないと思っても「そうするしかない」と思い込んでしまう。他の選択肢があることすらも思いつかないのかもしれない。他の人にはできても自分にはどうせ無理だと思ってしまうのかもしれない。「周り人がそうしている」という現象が、どれほど「自分もそうするのが当たり前」という選択肢として立ちはだかるのだろうか。次元が違う話になるかもしれないが、進学校に通う学生は大学に進学することが当たり前だと思う。親が社長だから起業することが当たり前だと思っていたという話も聞いたことがある。
環境に与えられる影響が良いものであるのなら、何の問題もない。それが自殺や人を傷つける方向に働くことが問題であり、根本的に考えるのなら自分が環境から受けた選択を「しない」と選び取れないことが問題である。本書を読んでいると「仕方がない」という言葉とともに海の仕事をし続けているのが見受けられる。それ以外の選択肢が見いだせずに生き続ける姿は正直憤りを感じたくなる。
しかし同時に、本書は全く別の問題を突きつけていくる。人が生きるということは何かを諦めることが必要なのではないかということである。そして人には苦楽に関係なく選んでしまう「宿命」のようなものがあるのではないか。
もし本書の主人公が本村実ではなく、兄弟の本村昭吉だったら、或いは漢那憲徳だったらそうは考えなかっただろう。人生良い時もあれば悪い時もある。それでもどうにかなるもんだ。そうした楽観的な結論に落ち着いたかもしれない。だが本書の主人公は本村実であり、その人生の選択は「そうするしかなかった」とういだけでは説明できない。
1ヶ月の漂流の末に救出された。常識的に考えればそこまでの瀕死体験をすれば二度と海に戻りたいと思わない。だが再びに海に出る。それも約8年のブランクがある。海でしか生活できないというのならすぐにでも海に戻るだろう。だが本村実には8年のブランクが有る。その間何を考えていたのだろうか。漁師としてしか生きられないと言うには8年の空白は長すぎる。そう考えてくると佐良浜の人たちが海から離れられない、これしかできないという言葉の中には生きることの中で、私たちが捨てられない生への許しのようなことが感じられる。言い訳としての「仕方がない」ではなく、苦楽を含んだ「したい・したくない」の両方を含んだ爽やかな「諦観」と呼べるものがあるように思えてならない。
山登りをする人は山が好きなのだろう、結婚した人はパートナーに対して好意があるだろう。しかしそれだけの感情だろうか。長く付合いがあれば様々な面が見える。嫌な部分のほうが多く浮かぶかもしれない。
私事を例に上げるのならば、私は5年間中国で生活をした、日本にはない歯に衣着せぬ言い方に清々しさを覚えるが、自分中心の振る舞いに腹をたてることもあった。むしろ不快に感じることのほうが多かったかもしれない。それでも振り返ってみればその自己中なところが憎めず親しみを感じている自分がいる。自分が悪く言う分には構わないが、他の人が言えば不快に思う。
本村実がどうして再び海に出たのか。本当のところはわからない。だが命を失いかけた遭難と再び海に出るまでにかかった8年という月日を考えると海への好意を想像せずにはいられなく。
他の選択肢が浮かばないという環境に依存しきった弱さと同時に苦楽を包みこんだ諦観の念を感じずにはいられない。望んだ人生を選ぶことができる。それは本当だと思う。だがそれと同時に諦めることで得ることもある。同じことをしているようで、意識が違うことで全く違う生き方になる。人の感情や生き方は環境に依存する。だがそれと同時に環境と如何に関わり、どのように感じるかを選ぶことができる。そうした矛盾した在り方を認識することが生きることだと本書を読んで考えさせられた。
そして最後に、今の私たちから見れば本書に出てくる人たちの生き方は時代遅れで貧しくて絶対に送りたくない生活に見えるかもしれないが、50年後の未来人が2017年に生きる会社に依存した生き方を見てどう感じるのだろうか。もしかしたら同じように感じるかもしれない。渦中にいるときには盲目である事を重々胸に刻んでいきたい。
投稿者 J.Sokudoku 日時 2017年5月29日
「漂流」
私は、本書に対して“海の漢のロマン”を勝手に期待していた。しかし、その期待とは裏腹に、本書は海に関わった人々が時代や環境に雁字搦めにされたという悲愴な物語だと私には映った。
そして、この「漂流」という物語は、一般人である私が対岸の火事視をするような事象ではないとも思った。
1.環境が思考を創り、そして思考が現実化する
“プライミング効果-連想メカニズム:自分では意識してもいなかった出来事がプライムとなって、概念、言葉、行動、感情に影響を与える(要約)- ~ファスト&スロー/ダニエル・カーネマン著より~”
この引用は、人間の脳とは無意識的に周囲から情報を取組み、影響を受け、そのことが思考や感情や行動に現れるようにできていると説明している。佐良浜の人々について幾度となく書かれている
“海の仕事をするしかなかった”
という宿命的とも取れる状況や
“いのちがかるい死生観”
といった価値観を生み出したのは、上記の脳のメカニズムで説明が出来るのではないだろうか。
佐良浜の人々は、生まれた時から海を見て、海に触れて、そして海に携る人達に囲まれて育つ。また、補陀落僧の漂流伝説や海から帰ってこない人達の話しを聞かされることも珍しくない。海は沢山の恵みを人間に与える存在であるとともに、人間の意志などお構いなしにとてつもない苦難を与える存在でもある。そして、離れ小島という地理的条件から限られた情報しか入って来ない。この環境が、佐良浜の人々の頭の中に海とは何かを刷り込ませ、更には閉鎖性が彼らの思考や行動をただひたすら海へと、海へと向かうことに拍車をかけ、結果として身も心も海とは切っても切れない現実を生み出したのだと思う。
では、海に身も心も占有されていたであろう村本氏が8年の歳月を経て再び海に向かった時の心境はどのようなものだったのか。私は、長旅から故郷へ帰る時に得られるような安堵感や懐かしさを最も感じたのではないかと思っている。
本村氏は、8年間の殆どを海について思い考え続け、そして自身の中にある“海の存在”が如何に大きいかを知ったのではなかろうか。海に出ないことからくる喪失感は、まるで
“自分が自分ではない”
感覚であり、苦悩や葛藤を繰返していたのではないだろうか。私は、海辺で一人虚空を見上げる本村氏の姿を想像してしまう。そして、
“こんな状態で生きていてもしょうがない”
という結論に思い至ったのではないだろうか。
“あるべき自分自身に戻りたい”
生まれた時から、すぐそこにあった海とは、本村氏の一部分、いやそれ以上の存在だったのだろう。一度は命を奪われかけたその海へ戻って行く。環境は人生において大きな影響を与える、時には一般的な死生観を超越するまでに。
2.私自身の人生における究極の漂流とは...
人生が海や航海に譬えられることは少なくない。人生の可能性が海の広さと、そして目的を持って生きることの重要性が航海と重ねられる。
“では、人生においての漂流とは何であろうか”
それは、
“意図せずに、とてつもなく困難で、軌道修正も難しい状況に陥ってしまうこと”
ではないだろうか。
ここから、まず私の頭に浮かんだ“人生における漂流者”の一例は、依存性のある薬物から抜け出せない人達である。多くの依存性薬物の常習者たちは、逮捕からの釈放直後は更生を誓うのだろうが、脳からの覚えた快楽への誘惑と失った人間関係が作り出す孤独感に耐えられず再犯に走る傾向が強い。絶対に犯してはいけない1つの過ちが自らを雁字搦めにする環境を作り出し、そこから抜け出すことを困難にする。再犯を繰返す薬物常用者たちは、間違いなく“人生における漂流者”と言えるだろう。
ただ、この手の漂流は、私も含め一般的には身近な話ではない。と思っていた矢先、先日参加した読書会(無葬社会)の最中に私は脳天をかち割るような衝撃に襲われた。
“無縁状態や孤独死って、人生においての究極の漂流ではないか?”
本村氏の1回目の漂流の原因は絶対に怠ってはいけない船の整備を楽観視して行わなかったことが直接的原因の漏水に繋がった。つまり、するべき行動を怠ったことが漂流を生み生死の狭間を彷徨わせたのだ。無縁状態や孤独死も、このするべき行動を怠ることの積み重なりが生み出すものではないだろうか。そして、私は連鎖的に「闇金ウシジマくん」が、“人生においての漂流者”について描かれているとも思ってしまった。人生においての漂流者たちの共通点は、するべき行動の躊躇。それこそが時間の経過とともに選択範囲を狭め、気づいた時には身動きが取れない、嘆いてもどうすることもできない状況を作り出すのではないだろうか。
最後に、私自身が常々自らに言い聞かせている一文を引用して今回の「漂流」の感想文を結びたい。
“自己コントロール能力-自己調節の失敗こそが、現代における主要な社会病理である- ~意志力の科学/ロイ・バウマイスター著より~”
~終わり~
投稿者 ktera1123 日時 2017年5月30日
「漂流」を読んで
・縁について
母方の祖母の実家は横浜の本牧で終戦後に埋立が始まるまでは漁師(網元)だったとのこと。祖母の話では本牧沖の東京湾は江戸前のよい漁場だったようで、よく魚がとれた話を生前に聞いたことがあった。また、元を遡ると和歌山のほうから出てきたとのこと。冒頭で「佐良浜の漁師」の祖先は補陀落渡海で熊野那智から南方の補陀落を目指して南海に旅立(漂流)した僧侶が辿り着いたのが始まりとあり、そこはかとなく親近感を感じて読み初めて暫くしたら、何気ない家族の会話の中で、妹の旦那の親父さんが元遠洋マグロ船の船員だったとの話が出てきて「シンクロニシティ」の凄さを改めて思い知りました。(すごい不思議だ。)
・本の内容から
P216に「『佐良浜の漁師』には島に残ってカツオ漁をつづけた人(生活の基盤となる歴史に支えられた陸上の地域共同体に所属する)と、遠洋船にのってその後も那覇やグアムでマグロ漁師として生きている人(完全に分割された独立した個人として海にいきる)の間にはどこか気質のちがいがあるように感じられた。」とあるように、帰属するコミュニティがあり帰るところがある人と、どのコミュニティにも所属せず個人として独立して生きている人の違いを醸し出すことで、漁師という限られた社会だけに限られたことだけの話だけではなく、現在の社会のなかで「漂流」していることになるのではないのでしょうか。
また、P400に「過去や未来に執着するあまり現在を犠牲にしがちな現代人の窮屈な生き方からは決して出てくることのない本音だと感じた。」とあるように、過去や未来にとらわれることなく今を生きることの大切さを訴えたかったのではないのでしょうか。
松尾芭蕉が奥の細道の冒頭で「月日は百代の過客にして、行き交う人もまた旅人なり。」と記したように、人生を目的の定まった旅人として過ごすのか、それとも目的もなくただ時の流れに身を任せて漂流して過ごすのか、そのようなことを考えさせられた1冊でした。
以上
投稿者 saab900s 日時 2017年5月30日
平成29年5月度 課題図書/「漂流」を読んで
37日の漂流という過酷な経験を乗り越えた後、再び海に出た。このようなフレーズの印象が強かったため、私はてっきり世界を股にかけた冒険家の話なのだろうと考えていた。それは陸でしか生活をしたことがない私の感覚を軸にした印象から導き出された想像であり、1度生死の淵をさまようことになってしまった海に再び挑戦するのは、「挑戦者」と書いて「アホ」か「ドM」のどちらかで読むのであろうと考えるからだ。だが、本を読み進めると「漁師」とあり、何故1度ならまだしも2度も危険を承知で海に足が向いたのだろうという大きな疑問が立ち上がった。私なら絶対に2度目は行かない。
本を読み進めると、自分のルーツ、生まれた町、親類縁者によってある程度の人生の方向性が決められてしまうのではないか?という仮定ができた。佐良浜の祖先が補陀落僧であるとされていることも驚きだが、その穂堕落僧そのものも信じがたい存在であった。すべては海に任せることであり、寧ろそれを誇りにしているとも感じることができるのが不思議である。
死の淵を彷徨った後、再び海に向かうその理由は、「自分にはそこしかない」という感覚であった。
レイヤーを上げてみると、自分の思い描いている世界でしか生存を許されていないと考えており、その中でもがいているように見える。そうして導き出された答えが「よし、もう一度海に出よう。何故なら、私は佐良浜で生まれ育ったのだから」というものでは無いだろうか。身近な漁師仲間、親戚一同、一族郎党が海に関係するのであれば、これが同調圧力と勘違いし、自分の残された道は海しかないと錯覚してしまうとも考えられる。私は根っからの陸で育った人間であるから、井の中の蛙よろしく自ら可能性を潰しにかかっている当時の本村実さんに言いたかった。「いやいや、生業を見出せる環境は海だけじゃないんですよ!!実さん!!」と。
さて、この構図は私が陸において生計を立てることができているという実績がある事に基づいて「漁師以外にも生計をたてられるんですよ」と言うことができている。しかし、本村実さんは自らが置く環境によって自分の生計は海で立てるべき。そしてそれこそ佐良浜人たりえるのだと言うのだ。その結果が大雑把な性格がウリの佐良浜人の気質をそのまま如何なく発揮することによって、2度目の漂流、そして、行方不明という結果に結びついている。知っている者にとってみれば、知らない者の行動が理解できない。補助をしても、知らない者がその補助そのものを拒否、又は、気づかずに流してしまうのだ。目の前には絢爛なご馳走が並んでいるのに箸を持とうとさえしないのだ。
これは、メルマガを通じて様々な情報提供をしてくれているしょ~おん先生と受信者との関係性に似ていると理解している。構図は同じく、情報はあるにも関わらず、今自分のいる場で狭い視野を用いて解決策を見出そうともがいているが、知識のある人、視点の高いひとからみると解決策は見えているものなのだ。
それでは、この視野の狭い人が解決を見出す方法は、自分が縛られてしまっている常識をゼロベースに考えること、信憑性のある情報には、自分のフィルターを通した判断だけで決断をせず、一歩引いて、レイヤーを上げて再度考えてみること。そして、エポケーをすること。もっとも大切なのは小さくても良いので一歩を踏み出すことに尽きると思われる。
小さな一歩は、次の扉を大きく開けるだろう。
私にも経験がある。メルマガ内で「体験を重視せよ」と受け取って以来、お金の振り方を体験系に大きく舵を取った。特に始めた楽器はゼロからのスタートだったが3年でLiveに出演する機会を得た。全てはところ構わず飛び込んだところから始まった。恥を恐れず飛び込むと意外に温かく迎えてくれ、得るものは大きな体験である。もちろん良い体験もあれば、苦い体験もある。
私は、佐良浜の人たちの性質は長く補陀落僧のルーツから連綿と海洋民族であるという自負を持って海の男として生業を求めるのは素晴らしいことだと思っている。魚を求める執念は、素潜りで20Mおも物ともしない強靭な肉体を作り上げ、爆薬で漁をし、自らがケガをすることも厭わない屈強な精神、南太平洋を縦横無尽に駆け巡り、新たな漁場を開拓するフロンティアスピリッツ。そのおかげで台風がきてもびくともしない頑強な住居を構えることに成功した。しかし、足りなかったのはひとつ。新しい価値観を受け入れることだったのではないだろうか。
歴史をみても、自分の主観を以てそれにしがみつく歴史は滅びやすく、柔軟に時代の情勢を嗅ぎ分けて、変化を受け入れながら時代を重ねていく方が結果的に長く歴史に留まる傾向があるのは周知のとおりだろう。これから、私も時代の流れを敏感に捉えながら、新しい価値観を取り入れていきたい。そしてそのチャンスは視点の高い人からの助言を受け止めて実践をしていきたい。
Just Do it!!
投稿者 H.J 日時 2017年5月31日
漂流
本書は私に様々な視点を与えてくれた。
色々書きたいことはあったが、4つにまとめた。
1.漁師への感謝
本書を読んで、率直な感想は「感謝」だ。
日頃、私たちが美味しく食べてる魚を獲るために命を賭けてる人がいる。
もちろん、本書で語られる時代と現在では、危険度は比べ物にはならない。
だが、命を懸けてるという意味では同じだ。
スーパーで何気なく並んでる魚も誰かが命を賭けて獲った魚である。
当たり前の景色も裏にある些細なことを知るだけで180度に近く見え方が変わる。
やはり読書とはすごいなと思った。
思い返せば、魚を捌く時や魚を食べる時、魚には感謝しても漁師には感謝したことなかった。
こういった視点は魚への価値観も変わり、さらに美味しく食べることが出来る気がする。
今週は市場に魚を買いに行こう。
2.佐良浜の漁師たちは幸せだったのか?
本書に出てくる漁師の方々は、誰かのためではなく自分のために漁に出ている。
生きるために命を賭けて過酷な漁に出る。陸に帰って来れば、酒と女に溺れる日々。
陸に住む私には到底理解の出来ない生活だ。
ここで一つ疑問が浮かんだ。
佐良浜の漁師たちの人生は幸せだったのだろうか?
答えは”YES”だと思う。
上にも書いたように私には理解の出来ない生活だが、きっと命を賭けてたからこそ見える世界もあるだろう。
もしかしたら、酒と女に溺れる陸での生活だけが漁師の人たちにとって「生きていると実感できる安息の時間」だったのかもしれない。
外から見ると、もっと幸せな人生があった様にも思える。
だが、それは私の考える幸福論で、佐良浜の漁師たちにもそれぞれの幸福論がある。
結局はその人の人生であり、その人がどう思考するかだから。
彼らは「漁なんて面白くない」とか不満を持ちつつも、きっと心の中では仕事(生き方)に誇りを持っているのだろう。
そうでなければ、それまでの自分の人生を否定することになるから。
3.実さんが海へ出た理由
同じ様に実さんが救出後にまた海へ出た最大の理由。
それは上と同じく”今までの人生を否定したくなかった”だと思う。
プライド、生き方、海が好き、その仕事しかなかった等の理由もあると思うが、一番はこれだと私は思った。
・漁師の父の元に生まれ、兄弟達も海に出て行った環境。
・義理父の鰹節工場で働いてたことがきっかけとなり海に出たこと。
・初めてマグロ船に乗った時のこと。
全部が実さんにとっては、かけがえのない人生の1ページであり、たとえ他人から否定されようが自分だけは否定したくなかったのだと思う。
4.実さんも”普通の人”だった。
他方で、佐良浜人特有の小さいことを気にしない豪快な性格から来るのかわからないが、
命を懸けた仕事で一番大切な危機管理能力がないことは残念だ。
自分一人の命であれば自業自得で済むが、船長として他人の命を預かる立場でありながら、整備不良の船に乗り続けるなどやってはならないことだ。
これは、単に実さんが船長の器ではなかった様に思う。実さんも結局は”普通の人”だったのだ。
・大丈夫と言いながら、自身の衰退と共に無くなる”自信”。
・”普通の人”が上に立ち、不満の募った下の”普通の人”から食われようとする様。
・噛み付かれても、既に謝ることしか出来ない状態。
以上を踏まえると、第一保栄丸は我々の時代に置き換えると、まさに”普通の人”が上に立つ会社だった。
読んでてそんな気がした。
本書は海と同じ様に、波があったり、様々な視点から見ると深さが深まる面白い書籍だった。
投稿者 diego 日時 2017年5月31日
おおらかに生き切ること
読書によって妄想する。
「こんなすごい環境で、こんなふうに生きていくのか…」
「こんな状況で、こんなアイディアが出るんだ。こんな選択をするんだ…」
そうやって、すごい!を妄想する。
漂流とは、どういうものだったのか?
漂流した船長本人に直接話を聞けないと判明するところから、この本は始まる。
取材を重ねていき、おぼろげながら「漂流」像が浮かび上がってくる。
「本村 実」を追いながら、もっと大きな範囲を追う。
時代を追い、地域を追い、人々を追う。
海で生きるということが、その人々にとって、どんな意味を持つのか。
何度も闇の深さを感じながら、何度でも追いかけている。
うーん。こんなふうにして、著者の妄想が私たちの妄想になっていくのですね。
実際には、思ったような筋書きにならなかったところが大きかったようで、
そんな著者の体験を追うしくみにもなっている。
そのおかげで、海の人々が当たり前に感じつつ語る内容がどれだけすごいのか、
うっかり見落としてしまうようなところも丁寧に拾っていて、
そういうところは、手引書でもありました。
(しょ~おんさんのセミナー受けてるみたいですね。)
これがすごい!と受け取る感受性は、本当に大事ですね。
本村さんが漂流後にも、海に出ることにしたのは、
ご本人に聞けたとしても、深い意味なんてないと仰ると思うんですね。
著者が追いかけてくれたことですが、海で仕事をして、それしかなくて、
目の前のことを生きて、自分なりのやり方で対応して、
それの繰り返しで、楽しみ、苦しみ、生き切ることなさったのだと、妄想しています。
ただ、それがどれ程すごい起伏のある人生だったのか、
どれだけ生死が隣り合わせだったのか、
過酷な中で生まれた退廃とおおらかさ。
それはご本人の軸で捉えると、「べつに…(すごくない)」なんでしょう。
でも私は、著者の体験を追い、それがどれだけのことなのか、妄想するのです。
生きる場所も死ぬ場所も海で、ただそこに向かって進んでいらっしゃったのではないか、と。
南洋漁業の時代を飄々と生きた存在として、その象徴として、
行方不明という、海への畏怖を感じさせずにはいられない特別な存在として、
今も生きていらっしゃるのではないか、と。
それを、海も、ご本人も、望まれたのではないか、と。
今月も、ありがとうございます。
投稿者 kawa5emon 日時 2017年5月31日
書評 漂流 角幡唯介 著
当初は、著者の取材対象である本村実、その人物の漂流記として読み進め、
奇跡の生還から、また何故に再度海に出るんだろう?の答えを探そうとしたが、
後半に進むに従い、著者自身も言及の通り漂流者は自分だと感じずにはいられなかった。
そして再出航に際しては、その生き様にある種の憧れも感じた。
毎回の課題図書のほとんどがそうだが、今回も全く異空間の思考回路を辿る旅だった。
海洋民としての佐良浜人の生活、思考習慣、人生、そして栄枯盛衰のカツオ漁、マグロ漁の歴史。
少し雑な言い方にはなるが、佐良浜人は、「今(現在)」を生き切っていると感じた。
著者が何度も言及するように、陸生活の思考回路では理解しえない生き方を本書で感じた。
本書より得た気付き
1、生きる喜びとは制限の中にこそ感じられるモノかもしれない。
本書の主人公である本村実、そしてその兄弟の人生には、その振れ幅に於いて、
相当凄まじいものを感じたが、それもこれも生まれ故郷では食べていけないために、
外に出る以外に選択肢は無く、且つ四方を海に囲まれた環境こそが生み出した必然の結果と感じた。
もし自分がその境遇に生まれたとしたら、十中八九、漁師になっていただろう。
海で生きる以外に選択肢は無い。正直、今の自分にはその境遇は想像できない。
しかし彼らの、壮絶ではあっても一本筋の通った生き様には、
そういう充実感を得られない現代の漂流者には、ある種の憧れに写るのではないかと思う。
生まれながらにして人生の選択を制限されたからこその、意思決定に於ける潔さ、
ブレの無さに少し憧れを抱いてしまう。
現代に於いて選択肢が多い故の悩み、終わりが見えない自分らしさ発見への旅、
そういう意味で、著者も自身をそう形容したが、漂流者は我々であると、
本書は問いかけていると感じずにはいられない。
自分は漂流者との認識を得ただけでも、本書を手にした意味は大きい。
2.人間の個としての自立が生きる躍動感を倍増させる。
主人公を筆頭に、佐良浜人の船乗りの自己責任感と言えばいいのだろうか、
その潔さ、次の行動への腰の軽さ、失敗した時の諦めと切り替えの速さ、
自分の人生に対する無駄な思い込みの無さなどは、より一層、
佐良浜人が今(現在)を生き抜いているとの印象を与える。
周辺事情への配慮よりも、自分の意思、決断の忠実な実行、
その自立の姿勢とそこから生まれる本書で紹介の各種のエピソードには、
生きる躍動感の大きな脈動を感じずにはいられない。
自立と生きる躍動感は比例関係。自立無しに、生きる躍動感は得られない。
3、保険が無い(掛けない)日常。
佐良浜人の時間の過ごし方に触れる時、人生に保険を掛けていない生き様だと感じる。
ここでいう保険とは、人生に於いて失敗を避ける、挑戦をしないなどという意味の保険である。
チャンスがあれば一気に捲し立て、チャンスをモノにするが、
チャンスが無いと明日のご飯にもありつけず、右往左往の生活を余儀なくされる。
稼ぎがあっても貯金に回さず浪費してしまい、その姿勢も終始変わらなかったことが、
生の輝きをより一層際立たせていると感じる。
しかしこの点に於いて、自身は佐良浜人のような過ごし方は全面的には実行出来ない。
特に家族持ちだったりすれば尚更で、逆に言うとそこが漂流者の問題なのかもしれない。
本書に於いてはあらゆる角度から書評が可能に思えて、まとめ作業に苦しんだが、
総じて所感としては、二度目の出航は本村実にとって従来通りに自然な判断であり、
且つ本人の意思に忠実に従った結果で、当人の望んだ次なる幸せへの一歩でもあって、
それ以上でもそれ以下でも無いと感じながらも、その余りに普通に感じさせる潔さ、
もっと言うと人間としての生死を超えたその判断の仕方、生き様に、
やはり一種の憧れと羨望を感じずにはいられませんでした。
今回も良書のご紹介及び出会いに感謝致します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
投稿者 fujita0728 日時 2017年5月31日
この本の内容を簡潔にまとめるなら、「2度の漂流をし、今現在帰ってきていない漁師の足跡、背景を追った本」だろう。
読むべきポイントは2つ挙げられる。「漂流の恐怖や極限状態の人間模様」と「何故漂流を経験しても再び海に出たか」の2つだ。
そして筆者が価値観を揺さぶられたのは 「漂流の恐怖や極限状態の人間模様」 も然ることながら、何故もう一度海に出たのか、というところである。
一度漂流など経験して海というものに恐怖を抱いてしまえば二度と漁など出たくなくなる、と考えるのが一般的だろう。
少なくとも筆者はそう思うし、陸を生活の基盤にする人間にとってのことと限れば異論はごく少ないと思う。
だが件の漁師は何故再び海に出たのか?
著者が一回目の漂流の当時の様子を調査し、近隣の人から人となりを聞いて語られることがらから筆者なりに考えてみた。
漂流を経験した漁師が再び海に出たその理由は、血筋と地域性が大きいのではないか、というのが本感想で述べたいことである。
その根拠は3点あり、1つ目は「言い伝えによる祖」の話、2つ目は「海を生活の基盤にする者としての性」の話、3つ目は「海を受け入れる地元の人々」の話である。
1つ目、 「言い伝えによる祖」 について。
本書の主な舞台となる佐良浜は言い伝えがあり、祖は補陀落僧であるという説があるという。
補陀落僧というのは宗教的教義から命を賭して航海し浄土世界を目指した僧のことだそうで、佐良浜の漁師が二度漂流したことと、祖先が漂流に命を賭した僧であることに著者は運命めいたものを感じている。
祖の話を真に受けるならば、そして血とともに「漂流へのスタンス」を受け継いでいるならば、…と仮定づくしになるが、我々陸の人間と漂流に対する根幹的考え方が違うのであれば「漂流してしまったことによるトラウマ」はイメージするよりも小さかったのかもしれないと考えたのである。
2つ目、 「海を生活の基盤にする者としての性」について。
件の漁師をはじめ、マグロ漁を営む人達は海の上が最も長い生活の空間になる。
陸の社会から隔絶された空間が与える具体的な影響は分からないが、マグロ漁に挑む漁師は荒い気質が多いということを著者も述べている。
海の上が生活基盤だからそうした気質を纏うのか、それとももともと陸の社会に馴染めないから気質だから海を選ぶのか、この因果関係は非常に興味深い。
因果の順序はどちらにせよ、件の漁師個人の話をする際に、気質を考慮することは重要だろう。
また、著者がインタビューした海外の人間にも一度漂流したが再度漁に出た人間はでてくる。これは重要な共通項ではないだろうか。
繰り返しになるが陸の人間と海に対する根幹的考え方が違う、という考えの根拠として、こうした海の人間の気質というものがあるのではないか、ということを挙げておく。
3つ目、 「海を受け入れる地元の人々」について。
著者の行うインタビューの中で、佐良浜の人たちは漂流したひとのこと・事実をドライに受け止めているという描写があった。
地元のひとは漂流を、それは海のことだし仕方ない、といった受け止め方をごく自然としており、明日は我が身ということも自然体で受け入れて生活しているようだという。
こうした地域性のなかで育ち、漂流し、帰ってきてまたその地域で過ごしていたということが、件の漁師の中に再び海へ出たいという衝動を呼び起こしたのかもしれない。あるいは、1度目の漂流を受け入れさせてくれたのかもしれない。
以上の3点を踏まえると、 漂流を経験した漁師が再び海に出たその理由には血筋と地域性が大きく影響しているのではないかと考えられるのである。
ここで伝えたいことは、1度の漂流を乗り越えさせるだけの引力が血筋・地域性にもしあるのであれば、自分自身においても同様に 血筋・地域性が影響しているだろう、ということである。
とするならば自分自身を分析し観察してみることでそれらの影響を想像し、省みることもできるかもしれないと思うのである。
以上
投稿者 sakurou 日時 2017年5月31日
~ 「漂流」を読んで~
本書を読み始めて、私は「永遠の0」を思い出した。というのも、37日間もの壮絶な漂流体験をした本村実がなぜ再び漁船に乗ったのかを探るため、情報が全く無い中、様々な人を訪ね、集まった情報を一つ一つ紡ぎあげ、本村実の本質に迫る点は、まさにあれだけ特攻に抵抗がありながら、最後に特攻を選んだ宮部久蔵の人物像に迫る、永遠の0のストーリーと全く同じと思えたのだ。
頼まれて乗ったのか、それとも自ら乗ったのか、妻と妹でも食い違う再び漁船に乗った動機もミステリアスだし、漂流者を救助したのが実は直前に漂流を経験していたという事実等、これがノンフィクションなのかと思える程、不思議な世界であった。
また、陸で仕事をする人間と海で仕事をする人間というのは根本的に人間が違うということを気付かされた。(沖縄に仕事を探しに行く世代になってからは別として)、佐良浜人は生まれながらに漁師として生きていくことが当たり前であり、幼少の頃からの遊びを通じて卓越した潜水技術など、 習得したもの全てが漁師としての血となり肉となる。それは単に職業上の適性というものではなく、まさに佐良浜人、池間民族のDNAということなのだろう。
漁師は死と隣り合わせというのは何となく認識していたが、非常に行方不明となるケースが多いことも本書で知った。とかくニュースでは「死者・行方不明者」と一緒にしがちだし、私もそう思っていたが、当事者にとっては違うし、まして頻繁に行方不明に遭遇する佐良浜人にとっては、独自の死生観が形成されるとともに、行方不明ということに対しても独自の価値観を持つのだろう。少し話は変わるが、3.11の関連で、何年も経って、骨一つのDNA鑑定の結果、子供と分かり、安堵した親の映像を見たことを思い出した。形見の一つにになれば、と苦労して角幡氏が持ち帰った救助筏のキャンバス地を妻は受け取らない。どこかで生きているはずと思うのもうなずける。消息不明になった時の「初動が遅れているので捜索範囲が広がり発見は困難になる」という漁師側の見方と「これだけ島があるんだからどこかの島にたどりついているはず」という家族の見方がその違いを如実に表している。池間民族の死生観を私なりに解釈すると「死と隣り合わせではあるが、死んでも連絡がつかなくなるだけで、あの世では生きている」という感覚なのかもしれない、ましてや行方不明者は死んだことが証明されていないので、死者よりもなおさら「どこかで生きている」という感覚が強いのだろう。
佐良浜人、また彼らと近い池間民族は補陀落僧ウタセリクタメナウが渡ってきたことにより創られ、彼らから信仰されている。補陀落僧はまさに「漂流」した僧であり、「漂流」によって生まれた民族なのである。行方不明が多いということは漂流が多いとうことであり、1回目の漂流では現地の漂流経験者により助けられる。まさに漂流が紡ぐ世界である。「漂流」したことで作られた池間民族のDNA。本村実も再び危険な目に会いたくないという気持ちより、佐良浜人としてのDNA、プライドを優先させて、再び漁船に乗ったのかもしれない。
本書を読んでいて、もう一冊、思い出した本がある。「卑怯者の島」。本村兄弟はなぜここまで、というほど、理由は様々だが兄弟が海で死んでいる。それなのに本村実は37日の漂流の末に生き残った。しかし時間が立てば経つほど、神平のように「兄弟は海で死んだのに、自分は生き残り、しかものうのうと陸で暮らしている」という風に感じ、それが時間が立てば経つほど重くなってきたのではないか?それが8年という長い年月に現れているし、その8年間に及ぶ逡巡、苦悩の末に、周りの意見が食い違うほど曖昧な形で漁船に乗る決意を固めたのだと思う。さらに、「半年程度」と語っていたところを見ると、その期間が長くなく、時期に兄弟と同じところに行けるという確信があったのかもしれない。
本書を通じて、私は「自分には自分の生まれ育ったDNAがあり、それを考慮しながら自分らしい生き方というものを大切にしなさい」という教訓を得た。佐良浜人は危険を顧みず、リスクを犯してでも大漁を狙う、冒険者やギャンブラーといった心意気を持ち、仕事も遊びも豪快なのが佐良浜人、池間民族らしさである。本村実は佐良浜人としてのDNA、本心に従い、また兄弟と同じ生き方を志すべく、再び漁船に乗り、再び漂流した。しかし、それは池間民族としては自然な振る舞いであり、周囲からの様々な声はあるが、結果的に家族も納得して生活を送っている。本書は実は優れた自己啓発書なのかもしれない。
今月も良い本に出会えました。ありがとうございました。
投稿者 tadanobuueno 日時 2017年5月31日
なぜ本村実氏は遭難後の航海に出たのか。
当初の自分なりの結論は、
育った環境、周りの当たり前に従った。
「これしかないのだ」と環境に流されてしまった。
「変われなかった」というネガティブなものだった。
課題著書を読んでいて、「こんな世界があるのか!」
「なぜそう考えるの?」といつも感じている。
今回のように死につながるものは、従来は「悪い結末」
と考え、なぜその環境をでないのか?でれないのか?
との思いを持って上からの目線で感想を書いてきた。
でも、本当に本村実氏にとってこの結末は不幸なのか?
佐良浜の人々は不幸なのか?
そもそもそれを私が決めることは誰かの為になっている
のか?と読み直していて疑問がわいた。
物事の良し悪しを一方的に決めていくこと。
ここから脱しないと、「こうあるべき」という、今の自分
の持つ思考に縛られて、変われない自分になっていくの
ではないか。
評価を下さず、受け入れてみる。
この視点を持って改めて佐良浜の方々をみてみた。
自分にとって気になったのは、著者も魅了された
「現在を犠牲にしない、目の前に流れる時間を生きること
に専念した」佐良浜の方々の生き方。
佐良浜の方々の行動力の良さはここに起因するのではないか、
過去・未来に囚われないことが「こうあるべき」に縛られに
くくしているのではないか?
目の前の時間を大切にして、行動を起こし、多くの体験を
して、佐良浜は繁栄を享受した。
この流れを整理していると、自分の中で直近のメルマガの
行動・体験・変態までの流れと繋がった。
では、佐良浜がこの繁栄のループから滑り落ちてしまった
のはなぜか?
自分の結論は、自分や周りにとって当たり前故、自分達が
環境で培ってきた強みに気付いていないこと、理解できない
ものを受け入れることができず自分の強みを活かせる新たな
世界を見つけることができなかったからではないか。
著者が「人間と土地とのしゃぶりつくようなエロティック
な関係」と表現していたが、全ての人間は自分の土地、
環境によってなんらかの影響を受けている。
環境に、習慣に縛られるのは佐良浜の人々だけでなく、
陸の我々も同じである。
住んでいる国、地域、職場、家族等々、自分を取り囲む
環境に縛られている部分がかなりあるのではないか。
自分の当たり前であること、その存在、良さに気付くため
には自分と異なる考えと接するしかない。
かつ、理解できないものの存在を認めることで、自分の
世界を広げ、自分の強みが活かせる新たな世界を見出して
いくことが必要なのだと改めて感じた。
私は子供が生まれてから自分の目の前にある子育てと向き
合い、現在、区の講座・NPO運営に携わるようになった。
その過程で様々な人と出会い、子育てとその取り巻く環境
につかってみることで、新たな視点を持つことができた。
もう一つ、自分の視野を広げてくれているのがこの課題
図書だ。
本を通して新たな視点を得ながら、且つ刺激的、独創的な、
素晴らしい、洗礼された文章を提供してくれる塾生の方達。
個人的に付き合いのある方からは課題図書をupせよと背中
も押して(蹴って)くれる。
これからもこの素晴らしき多様性の中に身を置き、現在を
大切にしながら、環境に左右されないしなやかな自分と
なる為、精進していこうと思います。
今月も素敵な本との出会いを戴きありがとうございました。
投稿者 BruceLee 日時 2017年5月31日
本書を読み始めた時、私の最大の関心は「何故、本村は二度目の航海に出たのか?」にあった。そして本書の展開はその謎解きがベースに進められるのだろうと期待していたのだが、読み進めるに従い、佐良浜の文化や風土、また
取材過程で出会う人々とのやり取りの詳述が冗長過ぎるように感じ、正直な所、次第に本書のポイントが何処にあるのか見えなくなってきてしまった。そして、著者が本書で何を言いたかったのかも呑み込めないまま初読を終えてしまった。
結果、私にとって「よく分からない1冊」で終わってたかもしれないのだが、あるキッカケで再読する事になった。言ってみれば私にとっての「二度目の漂流」となった訳だが、読み始めて直ぐ、序章の段階で一つの疑問が浮かんだ。そもそも著者は「漂流もの」を書こうと本村にアプローチした訳だが、もし本村が二度目の航海に出ず、現在は別の仕事をしながら普通の生活を送っていたらどうなっていたのか?
恐らく著者は本村本人から一度目の漂流の詳細を聞き取り、元々の目論見であった漂流体験記を書き上げただろう。が、本村家へ電話した時点で、彼が二度目の漂流の末、現在行方不明である事を知る。そこで次の疑問が浮かぶ。本人が不在では取材で得られる情報も乏しいため、この題材は断念して他を捜すのが普通ではなかろうか?が、著者はそうしなかった。それは何故か?初読時に印象に残った一文がある。
「私が本村実の漁師としての足跡をこれほどたずねまわったのは、このような不条理な海という自然にしばりつけられて生きてきた土地と人々の生き様に魅了されたからであった。と同時に、彼らにある種の妬みを感じたからでもあった(P. 420)」
これが本村
に固執した著者の動機だとすれば、本書は私の初読時とは全く別の読み方が出来ると感じたのだ。それは探検家を本職とする著者ならではの「探検記」としての読み方だ。Wikiによれば探検とは「未知の地域へ赴いてそこを調べ、何かを探し出したり明らかにする行為」とある。本村の育った佐良浜、マグロ漁船上での生活、本村の生き方は著者にとって「未知」であり、その未知に刺激され著者の探検魂に火が付いたのではないか?本村本人から直接話を聞けない取材活動とはなるが、何処まで明らかに出来るのか?そこに既存の「漂流もの」には無い、新たな「漂流もの」に挑んだ著者の探検記だと思えたのだ。
その観点で読み進めると初読時にはあまり感じなかったドロドロした人間臭さを所々で覚えた。何処に行き、誰と会い、どんな話を聞くか?時に思い通りに行かない取材過程を含む経緯において、著者は何を感じ、どう考えるのか。つまり前回は冗長と感じてしまった、それら取材活動の詳述にこそ、実は意味があったのだ。結果、取材で拾い集めた情報の欠片から、おぼろげながら何が見えてくるかは本書内に詳しいが、私が肝だと感じるのは、ルシアナによる人喰いの証言だ。ここで私が何を感じたかと言えば、
「漂流者」という言葉で一括りには出来ない、集団における個人の存在
である。著者は一度目の漂流者の何人かに直接取材する一方、本村本人が周囲に語った回想の情報も得る。漂流のキッカケとなる問題発覚の瞬間、フィリピン人が食料を直ぐ消費してしまった事、本村が援助は来ると言っていた事、鳥を殺して生で食べた話、小さなカニを食べて空腹をしのいだ話、フィリピン人たちが本村へ怒りを持つように至った経緯、喉の渇きは海水に入る事で癒された話、カメを逃がした話等々。それらが各人から語られるが、読み手にとってそれらは基本的に同じ内容である。彼らの前で起こった事実は一つなのだから当たり前だと捉えてしまいがちだが、そうではなく、やはり一人一人別の人間であり、その捉え方や重み、そして意味合いと解釈は異なるのだ、と気付かせてくれるのがルシアナ証言ではなかろうか。それ以前の取材では、まるで冗談の様に話す人間もおり、著者自身も信じ難い出来事と先入観を持っていたが、ルシアナ証言時の彼の態度の変化に、それまでの事実では見えていなかった隠れた真実を我々は感じ取る事が出来るのではなかろうか?そして本村のその時の、そしてその後の心情に思いを馳せる事が出来るのではなかろうか。事実ではなく真実。それはやはり各人と直接話してこそ得られるもの、という取材の意義を私はこの場面で強く感じた次第である。
と、結果的に「二度目の漂流」を試みた事で、私は初読時には得られなかった解釈が出来、それは同時に「1冊の本でも読み方は一つではない」と気付く事が出来た新たな読書体験でもあった。本書の内容自体は勿論、新たな読書の醍醐味を味わった気分であり、再読のキッカケを頂いた関係諸氏に感謝したいと思うう。有難うございました。
以上
投稿者 magurock 日時 2017年5月31日
『漂流』を読んで、ハーマン・メルヴィル『白鯨』の元ネタであるエセックス号の悲劇を思い出した。鯨に船を破壊され、救命ボートで漂流する生き残った乗組員たちの、極限状態においての壮絶な人間模様。
仲間の屍をむさぼり、生死をさまよいながら生還した者たちは、とてつもない地獄を見た。それなのに、体が回復すると、一部の者はやはり海に携わる仕事を続けるのだ。完全な陸人間である私には、とうてい理解できない。そして漂流時に船員に食べられそうになった本村実氏もまた、8年の空白を経て海へ出て、また行方不明になってしまう。
『漂流』では、池間民族のなりたちや海洋民の生き方が細かに書かれていたので、どうしてまた海へ?といった疑問に答えをもらえたような気がする。長年海洋民をしていると、それが仕事ではなく生き方になってしまうのだと、角幡唯介氏は書いている。好き嫌いに関係なく、海の仕事しかできなくなるのだ。
とはいえ、「理解できた」とは口が裂けても言えない。東京育ちである私では、まるでDNAに染み付いたように海で生きていく人たちの感覚が、本当のところでは一生わからないだろう。
しかし、戦前から続いていた佐良浜漁師の南方出漁も、今は行われていない。そう聞くと、「どうしてまた海へ?」と思ったくせに、ひとつの文化が消えてしまった寂しさを感じてしまうのだから、部外者とは本当に勝手なものだ。
ところで消息を絶った本村実氏は、その後どうなったのだろう。彼の奥さんと同様に、私もどこかで生きている気がしている。北朝鮮にいるのか、それともニライカナイにいるのか。
それか、これから起こる地球の大淘汰の後に必要な人間は、宇宙に連れ去られてそのときを待っているというから、タフで肝っ玉の据わった本村氏も、もしかしたら択ばれたのかも知れない。
アホなことを、と思いつつ、跡形も無く忽然と消えたという本村氏に、ついロマンや妄想を搔き立てられてしまう……
投稿者 akiko3 日時 2017年5月31日
「漂流」を読んで
海の男の世界は異次元のことに感じられ、読後に何が自分の中に残るのかと戸惑いつつ読み進めた。しょうおんさんが8月の戦争ものを読むことに備え、漂流を感じながら読んでみてと読んだ気がするし、宗教に興味があるから課題本でもそんな内容に触れたし、そしてなぜ漂流して生死の狭間から生還したのに再び出航したのか。それらがこんがらがって、2度読めともお達しがあったようだが、1度でギリギリ。
なぜ2度目の出航をしたのか、生きる方法、人格が、生まれた時から海ありきだったから切り離せなかったからだと思う。1度目の漂流で船長としての失格、殺したいぐらいの憎しみを向けられ、生きる価値がないとまで思ったかもしれないが、生き延びて、陸で生を実感して生きている自分を感じると、海上のような命が活気づいている生の実感はなかったのではないか?だから海にまた引き寄せられたのではないかと思う。今さえよければ、という船乗りの刹那的な日常は、感覚的にどうしても理解できないが、生まれた時からそんな土地・人・歴史から当たり前に刷り込まれている人達の細胞レベルの感覚は全然違和感がなかったのだろう。
生と死についても、私は死を具体的に考えられず、いつかくる死とは思っても明日はこないだろう、1年先でもこないだろう先の話と漠然と思っているのに対し、危険な仕事でも生きる為に選べず、手や足がない人達、昨日まで元気だったのにもういない人達がいる、ある日忽然と消える人の存在(命)が身近にあると、出航することは死に近づいているのかもしれないという覚悟があったのではないか?その上、そんな生活をしなければ飢えて生きていられない陸での生活。八方ふさがりのような生か死かを迫られる現実は、敵を殺さなければ自分が殺される中、生きたい、死んだ仲間の為に自分も追いかけないと生きているのも苦しい追い込まれる戦争の時代、卑怯者の島の視覚イメージはより強いのかフラッシュバックした。また、重油塗れの海に漂った戦艦大和の乗組員の体一つが広い海に漂う孤独に加え、狭い空間に1人外国人(敵に囲まれる)として存在する恐怖にどうやって耐えたのだろうか?
少女からメッセージを受け取った乗組員がいたが、本村実さんがウミガメを逃がしたのは、海に囲まれて育った佐良浜人の魂に刻まれている感覚からの自然の行為だろう。アラスカの白銀の世界で、人間と熊が会話をしていた時代のように、海と船乗りも対話し、命を預けていたのでは?
しかし、船から降り、酒と女と賭け事で散財する目の前の快楽に溺れる漁師の姿はやはり理解できないし、まとめようとするのもズレているようにも思う。そういう時代があり、そんな人達がいた、そんな生き方もあったんだねと感じるぐらいだ。いい悪いではなく37日漂い、助けられ、助けた人も漂流し助けられたばかりで、神に試されたと感じたという不思議なことがある世の中なんだ…と。
自分が背負った性の中、いかに生きるか、いかようにも選べる(はずだがまだ上手く思い描けず、現実にもがいている)世界なのだと、漂流せずに生きる為、智の道という羅針盤に合わせよりよい方へと進む。
伝統的な航海術“スターナビゲーション”によってハワイからタヒチを航海したナイノア・トンプソン氏が、見えない島をみる力が大切と語ったことが印象に残っている。最後は自分との対話なのだ。人生の岐路も自分との対話で道を選ぶのだし、人生の終わりもきっと自分との対話だろう。そして結果は委ねるしかないのだ。
投稿者 akirancho0923 日時 2017年5月31日
『漂流』を読んで
現代版の海賊のような生き様が描かれているのではないだろかと、
想像しながら読み始めましたが、実際はこの道しか生きる道を知らなかった、ゆえに
この道しか生きることができなかった生々しい人間ドラマだなぁと
感じました。
戦争もそうですが、”戦わねばならないそれ以外選択肢はないのだ”という
圧倒的な価値観が埋め込まれた人間模様は、本書を読んでいる私のように
限りなくその価値観から離れている人間からは、正直気分が悪くなるほど
異質に感じられ、なぜそのような生き方しかできないのか、という
クエスチョンを繰り返してしまいます。
しかし何度か読み返すうちに、選択肢がない、というのは
そういう結論を導くし、固有の価値観に導かれてしまうという
歪みを生み出すのだなと気づき、徐々に納得感が広がっていきました。
では私が本書のような状況に置かれた場合、どのようにすれば
2度目の「漂流」に向かうことがなくなるのか考えてみました。
結論は、やはり感動しかないだろうなという考えに至りました。
固有の価値観に匹敵するような、感動体験。
それを経験することができれば、新しい扉をのぞいてみようという
気持ちになれるし、自らの人生を顧みる余裕や
自分と対峙する時間が生まれ
生きてて良かったなぁ、と思える瞬間を味わえるのではないだろうか。
そして、その感動体験を誰かと共有できることで
更なる”幸せ”と呼ばれる感動につながるのではないでしょうか。
私自身、日々の日常の中で、周りから見ると小さな出来事かもしれませんが
発見しようと何事にもまずは興味を持つことで感動体験の種を見つけようとしています。
どのようなつながりを見せるのかわからないのが人生の醍醐味だと
少しずつですが感じている毎日です。
多種多様な価値観を身につけ、共有し、幸せな人生をこれからも
送りたいなぁとしみじみ感じました。
投稿者 2l5pda7E 日時 2017年5月31日
「漂流」を読んで。
どんなに痛い目にあっても、またやってしまうというのは往々にしてあるものだ。
しかし、一度死にかけた海へ再度行こうと思う思考回路には深い行動心理が敷かれていたはずだ。
人の行動原理の根本は、愛か恐れのどちらか二つしかない。
愛として考えられるのは、家族を養うためにお金を得るためと考えていたのではないか。
恐れとして考えられるのは、陸の仕事はすることができない、他の仕事ができないという観念を持っている事。
生まれ育った環境によって、人間はこうも違うのか。
爆発物を使って行う危険な漁をやっていたという佐良浜の歴史の中では、生と死が常に隣であったという環境が、楽観的視点を生み出したと考える事ができる。
1回目の遭難時、すぐ救助されるから大丈夫という思考や2回目の遭難に繰り出した思考はそこから生み出されたのではないか。
ノンフィクションの面白みが初めてわかった。
読者が想像なり妄想を思い浮かべる事ができないくらいかなり細かく描写されている、関係のある人の証言を並べ連ねる事により、まるで影絵の様に浮き上がってく様子が大変面白かった。
良書をご紹介いただき、誠にありがとうございました。
投稿者 Devichgng 日時 2017年5月31日
以下2点に興味を持って『漂流』読んだ感想を記載します。
[1] いつ助けが来るとも予期できない、死と隣り合わせとも言える筏での漂流から、どういう精神状態で生還したのか。
[2] そんな漂流生活を経験した上で、なぜ同様のリスクを抱える海に再び出たのか。
という2点について興味を持って今月の課題図書を読んだ感想を記載します。
[1] いつ助けが来るとも予期できない、死と隣り合わせとも言える筏での漂流から、どういう精神状態で生還したのか。
木村実氏の性格と1回目の漂流時の描写を見ると、
・少々のトラブルではびくともしない図太さと大胆さ
・どんなときも決して余裕を失わない
・何がおきてもつねに海のように悠然、泰然
・ユーモアとそれを生み出す精神的ゆとり
・必ず救助してもらえるという楽観論
というような記載があり、漂流という状況にも、決して希望を失ず、ネガティブな感情を立ち上げていないことがわかりました。いつ助けが来るともわからない絶望的な状況の中、木村実氏は落ち着ついて自身の心をコントロールしていたから、心が折れることなく生還できたのだと思います。
なぜこう読んだのかと言うと、メルマガで何度も紹介され、もちろん良書リストに記載もある『夜と霧』の中で、フランクル博士がアウシュビッツ収容所から生還したのとまったく同じ考え方をしているということに気がついたからです。
[2] いつ死んでもおかしくない漂流生活を経験した上で、なぜ同様のリスクを抱える海に再び出たのか。
行動の源泉は2つあると感じていて、1つは、[1]で記載したフランクル博士の考え方で、もう1つはA・マズローの自己欲求説です。
木村実氏は、船を失いはしたものの態度価値として漂流を不幸なイベントとは認識していなかったということだと思いました。
これだけでも十分説明がつきそうな感じがしましたが、別の考え方でも説明できないかと考えました。再読している、死と隣り合わせの漂流という出来事から「安全」という言葉が思い浮かび、そこからA・マズローの5段階欲求説で何かしらの説明ができないかと考えました。
木村実氏の行動を5段階欲求説に当てはめて考えていくと、第5段階の自己実現の階層であることがわかりました。
漁の最中は睡眠時間も少なく決して安全とは言えませんが、漁師という集団に属し、彼等から認められ、狙った成果を出しているわけですし、陸に戻れば当り前のように豪遊し、さらに船長という船の支配者として創造的な活動もしているからです。
ここから自己実現欲求説による再び海にでることを選択した理由の推測というアプローチは見当違いだったと一度は落胆したんですが、何だかひっかかると思って5段階欲求説を調べていくと、さらにもう一つ上の段階があることを知りました。
それは、第6段階の「自己超越」という階層です。
この内容を木村実氏に当てはめると、「自ら船に乗りたい」といった発言にも納得できる気がします。
氏の中では、生活するためのおカネ、他社と結びつく世間体、自尊心等の内的・外的の欲求は関係なく、海を喪失した空虚感を満たすために、より高次の海という一番距離を近くに感じる親密なるモノと一体化するということを目的とし、その達成だけを純粋に求めて自ら海に出ることを選択したという心境だったのではないかということです。こう考えると、一度目の漂流時、極限の飢餓状態の中ウミガメを食べない判断をしたというエピソードから、木村実氏にも海の声が聞こえるという神秘的な体験をしていたのかもしれません。
結局のところ、態度価値も自己超越の段階も、自分で価値を設定しそれを追求することで幸せになれるということを言っているのかなと感じました。
最後に、本書を一読したときに、漂流って体験したくないネガティブなイベントだと感じるだけで、これをどう楽しいモノにできるか?という思考実験をすぐに想起できませんでした。ここから、まだまだ意識をコントロールできていないということがわかりました。
今回の課題図書を通して、意識を変化させることを知っているだけで使いこなせていないとう状態に気づいたので、どんな状況であれ、いつでもサッと意識を変えることができるようにトレーニングをしていきたいと強く思いました。
投稿者 AKIRASATOU 日時 2017年5月31日
【漂流/角幡唯介】を読んで
本書を読んで改めて強く感じたのは「これからの時代は仕事しかしていない、それ以外に趣味や興味・関心の無い男は幸せになれないんだな」ということだ。
なぜ一度漂流し死にかけたにもかかわらず、本村氏は再度海へ出たのか?それはそこ以外に自分の居場所が無かったからではないかと思う。
本書に出てくる漁師達は小さい頃から漁師になるべくして育ち、その他に道があるということも知らずに盲目的に漁師になり、その狭い世界の中で誰よりも多く魚を獲る事を競った。それは日本人男性の大半が義務教育を終えた後なんとなく高校へ進み、なんとなく大学へ行き、就職し、会社という狭い世界の中で他者よりも良い成果を出すために家庭も顧みず働いた、という一昔前のサラリーマンと酷似していると感じた。
自分が慣れ親しんだ仕事をしている(またそれに付随する仕事の仲間と酒盛りをしている)時間こそが、自分が自分らしく輝ける時間であって、それ以外の時間は自分の肉体を通して見て・感じている世界だが自分の人生にはなっていないのだ。本書に出てくる漁師たちが海から陸に戻り、つかの間の休息の時間を酒盛り等で歓楽的に過ごすのと同様、一昔前のサラリーマンが平日は仕事をし、休日は接待ゴルフに興じ家にはお金を入れるだけで家庭のことなど何もしないという姿が重なって見えた。
本村氏は海が好きだった、船に乗ることが好きだったとは思う。ただ、それは他のことを知らずに生きてきたが故に、自分にできることは船に乗り魚を釣ることだという固定観念が染み付いてしまったけだけで、世の中には数多の仕事があるにもかかわらず本村氏にとって自分を満たしてくれる仕事というのは漁師以外にはなかったのではないかと思う。漂流しあれほど大変な目にあったにもかかわらず、なぜ本村さんはもう一度船に乗ろうとしたのか?というより本村さんは船に乗らずにはいられなかったのだろう。この時代を生きた人達は「ちょっと今から仕事辞めてくるわ」というメンタリティーは持っていなかった。それは本村さんに限った話だけでなく、本書に登場する漁師のほぼ全員が同じではないだろうか。本村氏が船に乗ること以外に趣味や興味・関心を向けられる、熱中できる何かがあったなら、二度目の漂流は無かったのではないだろうかと思う。
以上のような理由から、私としては仕事に一生懸命取り組むだけでなく、自分の趣味や興味・関心を広げるだけでなく、家族との関係、地域との繋がりといった事に今まで以上に気を配って、主体的に楽しみながら取り組まなければいけないと感じた。
投稿者 vastos2000 日時 2017年5月31日
東海大地震が発生すると言われて30余年。いつ地震が発生するかはわからないし、自分自身もじっと救助を待つ状況になるかもしれない。たまにエレベーターに乗った時などに、「今大地震が発生したらどうなるかなぁ」などと考えることがある。
もし、実際にそんな状況になっても、「もうだめだ」という心境にならなければ助かるチャンスはあると知ることができたのが、本書を読んでの最大の収穫だ。
この収穫を得るためにどのように本書を読んだかと言えば、以下のようなものになる。
「漂流」というタイトルだが、本村実の漂流をベースにした佐良浜の漁業史がこの本の多くの部分を占めている。先に内容があって、後からタイトルをつけるなら、なかなかこのタイトルはつけられないのではないだろうか。
とはいえ、タイトルを『漂流』としているのだから、漂流について考えてみた。
この本を読んでいて、第四章あたりで、結局この本に本村実本人は出てこないまま終わるなと感じた。実際行方不明のまま本書は終わっているので、読了しても消化不良感が残り、漂流しているときはどんな気持ちなのかを知りたく、別の漂流モノに手を出した。
その漂流モノは、漁船のトラブルで37日間漂流した武智三繁の記憶をもとに構成されてい「37日間漂流船長」(文章をまとめたのは『奇跡のリンゴ』の石川拓治)。
たったの2冊しか読んでいないので断定はできないが、1か月にもおよぶような漂流で生還するには、ある種の諦観というか、図太さのようなものが必要であるようだ。
本村実も救助されたときに衰弱はしていたが、精神に破たんをきたしてはいなかった。そして特に後遺症に悩まされることもなく八年後に再び海に出る。逆に精神的に深手を負ったべネールは若くして死んでしまった。
「37日間漂流船長」最後の方に、武智を診た医師の次のコメントがある。『潰瘍になった形跡がまったくないんです。僕は潰瘍くらいはできていると思った。(中略)潰瘍なんて、ちょっとした精神的ストレスで、すぐにできちゃうものなんだけどなあ』
つまり、武智は精神的ストレスをさほど感じていいなかったことになる。私だったら2日目くらいで口内炎ができ、4日目くらいで胃に潰瘍ができているだろう。
武智は漂流している間に多くのものをあきらめていた。途中で自分の命もあきらめた。だからこそ、生還できたと考えていると書かれている。
本書でも、それに類する記述がいくつかあった。
『「全然ちがう。彼らはね、冒険者なんですね。冒険者」』(p243)
『漢那招福も舌をまくほど、本村実には少々のトラブルではびくともしない図太さと大胆さがあった。さまざまな人物の印象を総合すると、彼はどんなときも決して余裕をうしなわない、何がおきてもつねに海のように悠然、泰然とかまえる人物だったようだ。』(p252)
『一人でも弱気になると、それは雪崩をうったように全員の士気に影響する。船員の気持ちから余裕がうしなわれれることが何より生還の可能性を小さくすることを、彼は経験的に知っていた。』(p339)
つまりはメンタル面が大きく生還率に影響するようだ。
いつ助けがくるか、そもそも助けがくるかもわからない。そんな状況下で命をつなぐためのメンタルとはどんなものだろうか?
「南方」や「ソロモン諸島」という言葉を見ると、太平洋戦争を想起するが、陸と海の違いはあれ、孤立無援状態という意味では共通するものがあるのではないか。
絶望的な状況下でも生還するケースはある。運が良いという要素も必要だろうが、運を呼び込む考え、心の在り様も生死を分けるのではないか。
陸であれば、「もう歩けない」と思えば実際に歩けなくなるし、海でも「もう助からない」と思えば救助される前に命尽きてしまうのだろう。
今、平穏な日常のなかで、全く実感なく、この漂流譚を読んだが、知識としてメンタル面が大事であることを知ることができたが、いざという時に行動(思考)に移せるだろうか?
正直、一人では自信がないが、守るべき子どもと一緒だったらできる気がする。
こう思うこと自体が、事実に対してどのように解釈するかはその人次第で自由であることの証左なのだろうけど・・・
投稿者 str 日時 2017年5月31日
漂流
・「漁師」といえば荒々しく、タフでカッコイイ男たちのイメージ。獲れたて新鮮な魚介類を船上で捌き、美味しそうに食べる。一般人にはそうそう出来ない体験だ。そんな彼らの姿に憧れを抱いた事がある人も少なくないと思う。けれど彼らの職場は”海”というとてつもなく広大で、一歩間違えば命を落としかねない、常に死と隣り合わせの世界だ。そんな所に放り出された時の恐怖は想像を絶することだろう。海の生物の恐怖、水の恐怖、飢えや乾き、なにより自分たちの安否を伝えることが出来ないというのが恐ろしい。近くを通り掛かった船には気付いてもらうことも出来ない。最初は救助への期待もあるだろうけれど、日が経つにつれ次第に「まさか救助は打ち切られたのでは?」という思いもきっと浮かんでくる。情報をなに一つ発信も受信も出来ない孤独感と、海にぽつんと浮かぶ救命筏の頼りなさ。本来は陸で生活している人間の無力さを痛感した。
・彼らの帰りを待つ家族が抱える恐怖もまた直視しづらいものだっただろう。安否の情報を知る術がないのは陸で待つ家族らにとっても同様だ。まるで海というより戦地。漁師というより兵士に近い感覚で彼らを見送り、帰還を待っていたのかもしれない。無事に生還できたとしても『自分のミス・格好悪い・恥ずかしい』と表現する人物もいた。まるで戦地から逃げ帰ってきたかのような扱いに驚き、漁師というものの厳しさを感じた。戦場では死の恐怖から発狂する人も少なくないと聞く。海上で漂流する彼らも『鳥を生で食べた』『船長を殺して食おうとした』『少女の幻影が度々現れた』などなど。正常な状態であったならば「あり得ない」と思うような体験をしている。けれど船員の一人は『恐怖は感じなかった』と語っていたが本当にそうだったのだろうか。やはりまともな思考で取る行動ではないと思う。結果的に生還し、過酷な体験も”笑い話“へと変えられるようになったのも、37日で救助されたという幸運でしかないだろう。もし運が悪ければ倍の74日目に発見されていたかもしれない。”もしも“の事を考えると自分には恐怖でしかないなぁ。
・本村実氏は壮絶な漂流体験の後、なぜまた海に出たのか。
「懲りないなこの人・・」と最初は思った。『おうちにずっといるのも疲れるから船に乗りたい』まるで子供の言い訳のようだ。あれだけの体験をしてなぜ?それは「もう二度と海に出たくない・・」ではなく「もう一度海に出たい!」という感情の方が大きかった。過酷な体験を遥かに凌ぐ“なにか“が彼の中にあったのではないかと思う。それが感動だったのか本能的なものだったのか。そこでしか味わえないであろう”なにか”はきっと本人しか分からない事なのかもしれない。
・普段当たり前のように食している海の幸。鮮度の良し悪し・人それぞれが感じる美味い不味いの違いはあるだろうけど、食卓に並ぶ“命“に詰まっている重さへの感謝を改めようと思う。
ありがとうございました。
投稿者 gizumo 日時 2017年5月31日
「漂流」角幡唯介著を読んで
「漂流時の体験とその救出活動が感動的に語られる」というおおよその期待が大きく裏切られた。その内容なら『課題本』にならないだろうし、このボリュームもないだろう。
戦争を挟んでの沖縄におけるマグロ、カツオ漁のグローバル化は知っているようで全く知らない世界であった。日本人は船長一人、言葉の壁も高く通常のはコミュニケーションさえ心配される。さらに、船の規模も驚きの小ささながら逆に動くお金は大きい。
佐良浜人に代表されるような海洋民族の独自性は海の神秘性そのままで、さらにニライカナイやウミガメ、捜索時の閃光などおとぎ話のような世界が広がり怪しい系満載でぐいぐい引き込まれつつ、どこか物悲しいのが不思議であった。
極限状況での著者の分析は目から鱗であり、「アイムソーリー」の言葉が重かった。人生そのものの過ちさえ感じてしまう極限状態とはなかなか経験できるものではないだろう。また、著者の出身地や時代性との対比も興味深かった。さらに、漁師の世界が語られる中で「何か引っかかりがある…」と感じていたが、途中でハタと気がついた。「料理人の世界に似ている…」と。ぼくとつでシャイ、口べたで照れ屋さん、でもって頑固、時には興味津々で天真爛漫。そんなキャラクターが多い点や、広いようで狭い世界。ほとんど抜けることなくその世界で生き続け、現場を転々とし、技術だけで誰とでも繋がり仕事をする(料理を生み出す)、一部はオーナー(経営者)となる人もいるが現場ひと筋も多い。
しかし、佐良浜漁師が決定的にちがうのは、それに地域性が大きなウエイトで加わることだろう。
本村実氏の漂流に関して丁寧に細密に調査し、それを取り巻く人間模様と生き様のノンフィクションであるが、自分はどこかの島で彼は飄々と暮らしている気がする。そしてふらっと戻って来てほしい…。
投稿者 truthharp1208 日時 2017年5月31日
「漂流」(角幡 唯輔)を読んで
本書で最も印象に残った一文
「そのような死が間近にある生活、常に死を意識しながら展開される生に、私は畏敬とも畏怖ともつかない気持ちをいだいた。」(P134)
私が過去に死を意識した経験と言えば、20代前半の頃、歩行者信号が青に変わって横断歩道を渡りはじめようとした時に目の前をダンプカーがスピード出して通り過ぎていき、一歩間違えたら跳ねられて即死していたかもしれないとぞっとしたことくらい。
最初に本書を手にした時、海を漂いながら、いつ助けが来るかわからない状況で生き延びるとはどういうことかを感じる目的だったが、読み進めていくうちに下記の気づきがあった。
1,新たな沖縄を知る。
本村実氏や佐良浜の人々の生き様を通じて、戦後の沖縄を垣間見ることが出来た。
奇しくも、今年は沖縄が日本に返還されて45周年の節目の年。新聞では毎日のように普天間基地移転問題をはじめ、沖縄に関する記事を目にしている。最近では、八重山日報が沖縄本土でも入手出来るようになったことも大きなトピックになっている。
また、沖縄県が全国でも有数のマグロの産地で、水産関係者知名度を上げようとしていることに今さらながら驚いた。(マグロの産地と言えば、三崎か大間くらいしか思い浮かばなかった。)
2.佐良浜の漁師の生き様
本村実氏が漁に出て、漂流して助かった後、しばらく海に出ていなかったため懲りたのだろうと思ったら、(最初の漂流から)8年後にまた漁に出て、戻って来なかった。私としては2度と漁には出たくない、と感じるものだが、本村氏は自分の力を見せるのは海しかないと肌で感じていたからこそ出来たのであろう。
佐良浜の漁師達はダイナマイトを使って漁をしたり、稼いだお金は飲みに散財したりと、破天荒ではあるが、根っこには海を愛する心、海しかないというブレない自分軸をを持っている。
窮地に立たされた時、冷静に対応出来るか、あるいは日々の生活の中で自分軸を保てるか、考えさせられました。
今月も良書をご紹介頂き、ありがとうございました。
投稿者 jawakuma 日時 2017年5月31日
「漂流」を読んで
スゲーーーー! まずはこの一言です! 本当にぶったまげました!
私が仕事を始めた頃、「この仕事やるか、マグロ漁船乗るかどっちがいいんだ!?」と冗談で先輩から脅されていましたが、当時は漁業の過酷さと1年の大半を海の上で過ごすことだけにしか着目していませんでした。しかし当のマグロ漁船の漁師は37日間も漂流し極限状態にいたってもまた海に戻ることを選んでいます。その心境が本書を通して垣間見ることができました。
沈没の前後や漂流の前半の心境も落ち着いた様子にも驚きましたが、常に海上にいる人からしてみたら救助が来ると言われればそれくらいの心境なのかもしれないと理解することができました。しかし後半はちがいます。冗談じゃなく人が人に齧り付く極限状態で、かまれた船長も涙を流しひと言「ソーリー」です。
みんなが楽しく沖縄へ旅行で訪れた際に感じる海洋民族の独特のおおらかさは判っていましたが、本当のその価値観がここまで地域性、民族性に根付いたものなのだとはじめて理解できました。中でも佐良浜の属する池間民族の間の宗教観が大きく影響を及ぼしていることを初めて知りました。中でも鎌倉時代から続いてきたという補陀落層の話では即身仏の海上版ともいえる極楽浄土思想が絡んでおり、その思想が先祖代々脈々と池間民族の血に流れているということでした。海から富も災厄も与えられ、海を崇め恐れ、海で生きそして海に消えていく。そうやってずっと暮らしてきたんですね。
武勇伝もすごい!素潜り20m、ダイナマイト漁、沈船漁り、数回の航海で御殿、ジョニ黒で手を洗う、愛人10人さらに奥さんにその愛人との間にできた子を見せて許される、これはアーミッシュも赦しません普通は(笑)そしていくら稼いでもパーーーっと使ってなくなったらまた海に出る。すごい豪胆ですね。そういう人は経済観念が壊れているかおバカなのかと思っていたのですが、佐良浜の漁師はみんながそうだということで、海にいけば魚が捕れるので食いっぱぐれることはないというその心持ちから、何とかなる、なんくるナイサーの行動なのでした。そしてその浮き沈みを味わった誰も住まなそうな古い事務所後に暮らす人へのインタビューがまた凄かったです。何しろ手土産が食パン1斤ですから!なにそれ!?本当に同じ日本、同じ時代での話なのでしょうか?これは沖縄の平均給与がダントツで一番下になる訳ですね。魚釣ってきて食べればまあいっかですよ。でも著者はそこでも優れた洞察をみせていました。過去の栄光にしがみついたり、来る未来を過度に恐れたりで現在を思い切り生きることができない現代人と比較し、全力でその瞬間を楽しむことにかけてきたその人の人生を羨望にも似たまなざしで眺めていたのです。常識で考えると食パン1斤で喜んでる人をうらやましく思うってどういうことなんでしょうか。やはり土地柄からくる価値観というか思考回路の背骨の部分の構造が全くちがう、それは先祖代々延々と続いてきた宗教観、幼少期の思い出、海を漁を疎み憎みながらもそこから逃れられず愛し続ける民族性があるのでした。
メディアの海難事故の取り上げ方にも元新聞記者の筆者からとても的確に指摘が示されていました。確定しないものは報道できない。2~3日無線連絡が無くても普通。陸上とは異なり3日で捜索は打ち切り。そのまま海に消えている人達は北朝鮮拉致の人達の何倍もいるんだということに初めて気づかされました。
また本書では海洋国家日本・沖縄の遠洋漁業の歴史を当事者の目を通してみることができました。海上には国境がない、法律もない、人の命も軽いようなメディアでは決してかたることのできない言葉が当事者の目を通して語られていました。
高野さんの冒険部の後輩の著書だったわけですが、
行方不明になった漁師を追いかけた高知~フィリピン、ソロモンに及ぶ海を舞台にした男たちの冒険譚を味わうことができました。
今月も良書をありがとうございました。
投稿者 haruharu 日時 2017年6月1日
漂流
本村実が、8年後、再び漁に出たのはなぜか?
そういう気質を持ってしまった以上、そういうところにしか働けない感覚なんだろうなと思う。社長やってたらそういう思考になってるので次のところでも社長業やってしまうように、また本村実も再び漁に出たんではないだろうか。
男たち、佐良浜人たちに共通して一つだけすごいなぁと思ったことは、内部にかかえる心理的版図は空間的に大きく広がる雄大な気質、周囲何千方キロメートル単位で広がる太平洋の島々を心の領海内にかかえこんでいるということでした。
そういう内部にかかえる雄大な広がりに女性たちは、富美子さんは例えご自身の旦那様でも近づけない入り込んではいけないキョリのような何かを感じ、尊敬の念を抱いていたのか?平社員が社長や会長に会ったときにスケールの大きさの違いを肌で感じる感覚なのか。
それにしても登美子さんが本村実に話しかける言葉使いの丁寧さに感動した。
他の会話はいかにも佐良浜言葉なのに登美子さんの実さんへの接し方は他の人と違う感じがした。
最後に、本書にでてくる平良とは私が子供時代を送ってきた土地である。
怖くて近寄れなくて話しかけられないと毛嫌いしてた佐良浜人を何十年も経ってこの本を通して理解していくことになるとは。
佐良浜人が宮古島全体の経済を支えていたという1960年から2000年の間には、私や兄弟、従妹たちが育った期間に該当する。間接的にお世話になってたということが今初めてわかったことに驚き、感謝したいと思います。
ありがとうございました。
投稿者 chaccha64 日時 2017年6月1日
「漂流」を読んで
死ぬ一歩手前までを経験したのに、本村実はなぜまた漁にもどったのか? 普通の人間なら二度と漁に出ることはないだろうと思う、しかし、救助後の病院で世話になった山井さんに「小さいころから海で囲まれた環境で育ったから、船には乗るだろう」と語っている。最初から、海に戻ることが当たり前だと考えていた。というか、海、漁と関係するのが当然のこと、息をするようなことだという感じなのだろう。
これは、本村実だけだはない。著者がインタビューした漁師はにはどこかそんな感じを受ける。マグロ両氏だけでなく、沈船あさり、ダイナマイト漁、カツオ漁に関わった人にもあるように思う。
そして、これらの人は海に対しての神聖さ、憧れ、敬意がある。そのため、海と関わることが当たり前だと思っているのではないだろうか。それは、本村実の漂流を漢那招福が「自分のミス。だから恥ずかしい。」と言っている。海に対して真摯に向き合わなかったことを言っている。船の整備をしなかったし、無線が壊れたままで操業を続けたことを言っているのだろう。
これは、池間民族だけではない。最初の漂流で救助したギニャレスも、救助前に漂流していた。そして、漂流後すぐの漁で本村実たちを救助している。この人も同じく、海に吸い寄せられている。海でしか生活できない、海でないと生きていけない、生きていることがわからないという感じなのだろ。
しかし、この感じ、想いがわかりません。海とかかわりがなく生活してきた自分としては海の対してそこまでの想いがわからない。お金にはなるかもしれないが命の危険にさらす必要があるのか。(通常とは危険度が違いすぎる) 魚価が低くなったのであれば、別の方法、養殖等を考えるとかもあるし、陸で職業もあるとい思う。結局、「小さいころから海と関わり」を持たずに暮らしてきたものには本当のところはわからないという気がします。