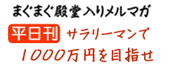-------------------------------
過去の課題本とコメントはこちらから
-------------------------------
第149回 エネルギーをめぐる旅――文明の歴史と私たちの未来
第146回 健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて
第143回 「風の時代」に自分を最適化する方法 220年ぶりに変わる世界の星を読む
第142回 未来の年表 人口減少日本でこれから起きること/未来の年表2 人口減少日本であなたに起きること
第141回 人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている
第139回 投影された宇宙―ホログラフィック・ユニヴァースへの招待
第135回 考える脚 北極冒険家が考える、リスクとカネと歩くこと
第132回 ドキュメント 戦争広告代理店~情報操作とボスニア紛争
第130回 もう一つ上の日本史 『日本国紀』読書ノート: 近代~現代
第128回 小林一三 - 日本が生んだ偉大なる経営イノベーター
第127回 山口 周 の ニュータイプの時代 新時代を生き抜く24の思考・行動様式
第122回 起業の天才!: 江副浩正 8兆円企業リクルートをつくった男
第121回 NO RULES(ノー・ルールズ) 世界一「自由」な会社、NETFLIX
第120回 LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界
第117回 PIXAR <ピクサー> 世界一のアニメーション企業の今まで語られなかったお金の話
第116回 「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考
第114回 14歳で“おっちゃん"と出会ってから、15年考えつづけてやっと見つけた「働く意味」
第111回 冨田和成 の 資本主義ハック 新しい経済の力を生き方に取り入れる30の視点
第110回 ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現
第109回 インテグラル・シンキング―統合的思考のためのフレームワーク
第108回 シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成