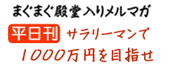投稿者 mkse22 日時 2021年10月31日
美味礼讃を読んで
『いずれにせよ、彼が静雄に見返りを与えることなど不可能だったのだ。』(Kindle の位置No.5926-5927)
小宮哲夫の退職に対する辻静雄の気持ちを表現したものだが、忘れることができない一文だ。
なぜなら、私も小宮哲夫と同じ立場だからだ。
私にも多大な恩を感じながらも見返りを与えることができない人がいる。それは私の両親である。
この一文は私に対する両親の気持ちと同じではないかと思ってしまい、
さらっと読み流すことができなかった。
辻静雄は自分の学校の生徒や教員に対して大金と時間と手間を際限なくかけてやっていた。
フランスや香港への海外研修や食べ歩き旅行など、その時必要なことだったとはいえ、
相当な費用がかかることを行ってきた。しかし、小宮哲夫のように、
必要な技術と知識を習得したら彼を裏切る形で去るものも多数いた。
私は研究者になるため大学院まで進み、29歳まで学生だった。
学生の間は、(奨学金を借りていたとはいえ)親からも金銭的援助をしてもらっていた。
しかし、結局、研究者として芽が出なかったため、大学院を退学し一般企業に就職した。
正社員として就職したことにより、一人で生活していくためには
十分なお金を稼ぐことができ、奨学金の返済は進んでいるが、
親への返済はまだできていない。(なお、両親からお金を返せとは言われているわけではない)
ただし、小宮哲夫たちと私では違う点がある。
まずは受け取った金額だ。小宮たちが受け取った金額はほぼ返済が不可能な状況なのに対して、
私が親から出してもらった金額は、大金だが返済ができないほどではない。
奨学金の返済が完了したら、そこから返すことも可能なわけだ。
もうひとつは裏切り方だ。
彼らは退職という選択をすることを通じて自らの意思で辻静雄に裏切ったのに対して、
私は研究者になれず期待に背いた意味でやむなく両親を裏切ってしまった。
小宮哲夫の裏切りをきっかけに、辻静雄は心の底では他人からの見返りを期待したこと、
さらにその見返りを得ることができないことに気づいた。
そのことに気づいた彼は、他人に期待しなくなり、さらには自分の体にも期待しなくなる。
そして、すべてのことを受け入れるようになり、最終的に次のような結論に至る。
『結局、人間にできることは、自分がやってきたことに満足することだけなのだ』(Kindle の位置No.5927-5928)
もし、私の両親も辻静雄と同じ結論に達していた場合、私は彼らにどう接すればよいのだろうか。
少なくとも、私からは「私への金銭的援助はあなた達(両親)がしたかったことであり、
その結果はどうであれ、それを受け入れてね。」とは言えない。
ここでよく考えると、私が両親から与えられたものはお金だけではない。
もっと大きなものが与えられている。それは私の命だ。
これは同レベルのものを返しようのない巨大な贈り物である。このことはすべての人にも当てはまる。
この世で生きている人は、もれなく親から命という返すことができないほどの巨大なものを与えられている。だれもが小宮哲夫のように、十分な見返りを与えることができない立場にいるわけだ。
ただ、お金とは異なり、命は親から子へ子供へ強制的に与えられたものだ。
そうすると、親は子供に対して、「この世に生んでやったのだから、その恩を返せ」と要求することが可能なわけだが、子供からは「生んでくれと頼んだわけではない」と反論されるかもしれない。
特に、社会や学校が合わず、生きることに苦しんでいる子は、生んでくれたことに対して感謝すらしてないかもしれない。
この子供の反論には親は再反論しにくいだろうし、こういうやり取りが続くと親子関係がおかしくなるかもしれない。
このように、見返りをすることが不可能なものを与えた場合、与えた側は、自身の行動が自己の満足を満たすためであることを理解し、見返りを要求しないことが重要だ。それでは受け取った側はどうすればよいか。受け取った側は、与えた側に対して、まずは感謝をして日々を生きてするだけでよいのではないか。というかそれ以外のことはやってもあまり意味がないだろう。
なぜなら、出来る限り見返りをするでもよいのだが、受けとったものとその見返りの差が大きすぎるため
差が埋まることはなく、結局、ただの自己満足になってしまうような気がするからだ。
与えるものと受け取るものの価値の差が大きすぎる場合、交換が成立せず、ただの贈与になってしまう。
そして、この贈与が、(辻静雄が日本のフランス料理界の発展に多大な貢献をしたように)
文化水準の向上に必要なことだということが理解できた。
今月も興味深い本を紹介していただき、ありがとうございました。